JFC講座
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、ファクトチェックやメディアリテラシーを学ぶための様々な講座を提供しています。2024年春には一般向け、教育者向けの講座も開講する予定です。また、学生向け、シニア向けなど世代別の講座なども計画しています。
新しい講座の案内やファクトチェック記事などをメールで受け取りたい方は、こちらのメール会員(無料)にご登録ください。
ファクトチェック講座
理論から実践まで学ぶJFCファクトチェック講座
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、YouTubeで学ぶ「JFCファクトチェック講座」を公開しました。誰でも無料で視聴可能で、広がる偽・誤情報に対して自分で実践できるファクトチェックやメディアリテラシーの知識を学ぶことができます。
理論から実践まで学べるJFCファクトチェック講座 20本の動画と記事を一挙紹介
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、YouTubeで学ぶ「JFCファクトチェック講座」を公開しました。誰でも無料で視聴可能で、広がる偽・誤情報に対して自分で実践できるファクトチェックやメディアリテラシーの知識を学ぶことができます。 理論編と実践編の中身 理論編では、偽・誤情報の日本での影響を調べた2万人調査の紹介や、間違った情報を信じてしまう背景にある人間のバイアス、大規模に拡散するSNSアルゴリズムなどを解説しています。 実践編では、画像や動画や生成AIなど、偽・誤情報をどのように検証したら良いかをJFCが検証してきた事例から具体的に学びます。 JFCファクトチェッカー認定試験を開始 2024年7月29日から、これらの内容について習熟度を確認するJFCファクトチェッカー認定試験を開始します。誰でもいつでも受験可能です(2024年度中は受験料1000円、2025年度から2000円)。 合格者には様々な技能をデジタル証明するオープンバッジ・ネットワークを活用して、JFCファクトチェッカーの認定証を発行します。 JFCファクトチェッカー認定試験
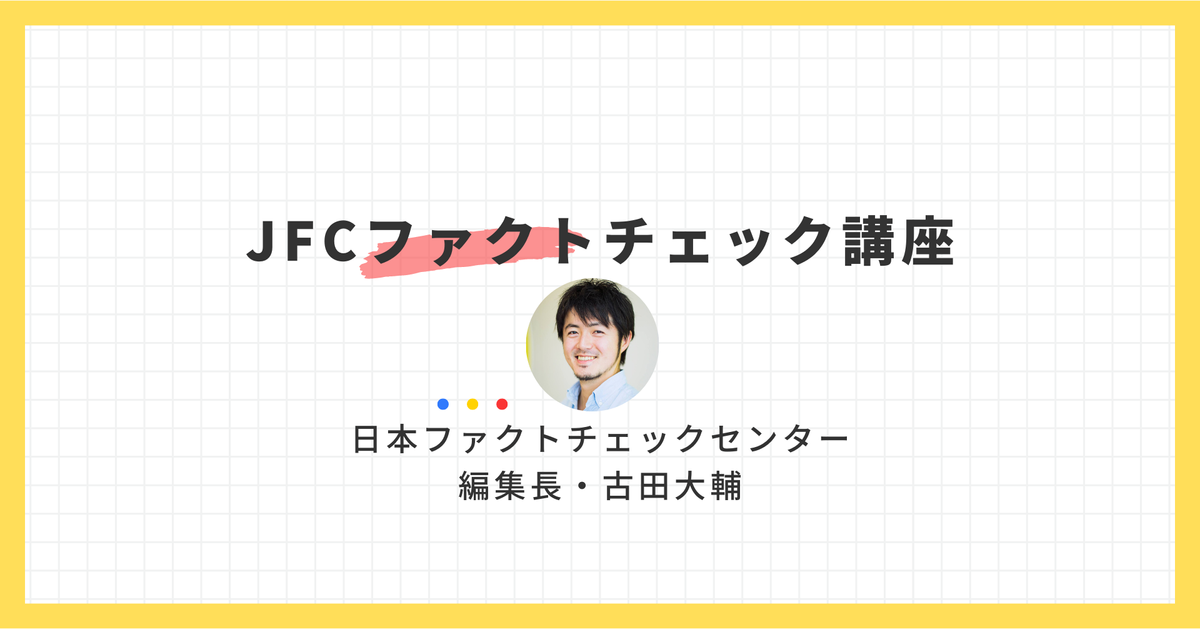
JFCファクトチェッカー認定試験
日本ファクトチェックセンター(JFC)はJFCファクトチェッカー認定試験を開始します。YouTubeで公開しているファクトチェック講座から出題し、合格者に認定証を授与します。
JFCファクトチェッカー認定試験 教材と申し込みはこちら
日本ファクトチェックセンター(JFC)はJFCファクトチェッカー認定試験を開始します。YouTubeで公開しているファクトチェック講座から出題し、合格者に認定証を授与します。 拡散する偽・誤情報から身を守るために 偽・誤情報の拡散は増える一方で、皆さんが日常的に使用しているSNSや動画プラットフォームに蔓延しています。偽広告や偽サイトへのリンクなどによる詐欺被害も広がっています。 JFCが国際大学グロコムと実施した2万人を対象とする調査では、実際に拡散した偽・誤情報を51.5%の割合で「正しいと思う」と答え、「誤っている」と気づけたのは14.5%でした。 自分が目にする情報に大量に間違っているものがある。そして、誰もが持つバイアスによって、それが自分の感覚に近ければ「正しい」と受け取る傾向がある。インターネットはその傾向を増幅する。 だからこそ、ファクトチェックやメディアリテラシーに関する知識が誰にとっても必須です。 JFCファクトチェック講座と認定試験 JFCファクトチェック講座(YouTube, 記事)は、2万人調査を元に偽・誤情報の拡散経路や
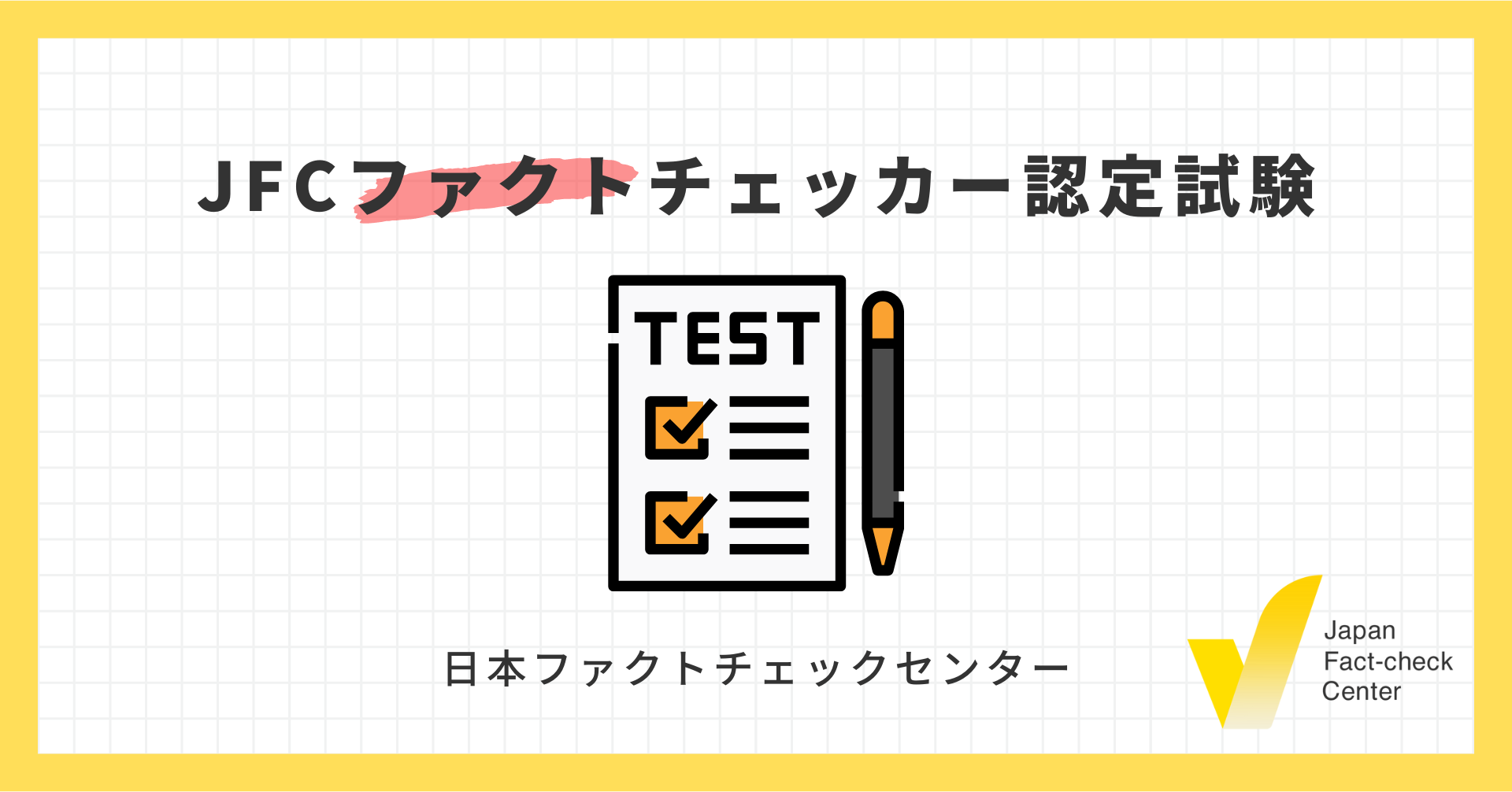
JFCファクトチェック講師養成講座
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、ファクトチェックやメディア情報リテラシーに関する講師養成講座を月に1度開催しています。講座はオンラインで90分間。修了者には認定バッジと教室や職場などで利用可能な教材を提供します。
JFCファクトチェック講師養成講座 申込はこちら
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、ファクトチェックやメディア情報リテラシーに関する講師養成講座を月に1度開催しています。講座はオンラインで90分間。修了者には認定バッジと教室や職場などで利用可能な教材を提供します。 次回の開講は12月20日(土)午後2時~3時30分で、お申し込みはこちら。 https://jfcyousei1220.peatix.com 受講条件はファクトチェッカー認定試験に合格していること。講師養成講座は1回の受講で修了となります。 受講生には教材を提供 デマや不確かな情報が蔓延する中で、自衛策が求められています。「気をつけて」というだけでは、対策になりません。最初から騙されたい人はいません。誰だって気をつけているのに、誤った情報を信じてしまうところに問題があります。 JFCが国際大学グロコムと協力して実施した「2万人調査」では実に51.5%の人が誤った情報を「正しい」と答えました。一般に思われているよりも、人は騙されやすいという事実は、様々な調査で裏打ちされています。 JFCではこれらの調査をもとに、具体的にどのような知




