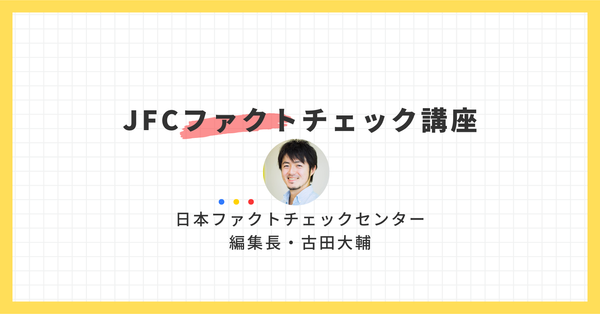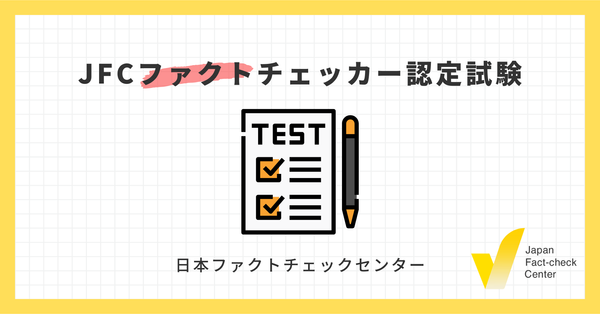ファクトチェックと「プリバンキング」 偽情報対策はいろいろ【JFC講座 実践編9】
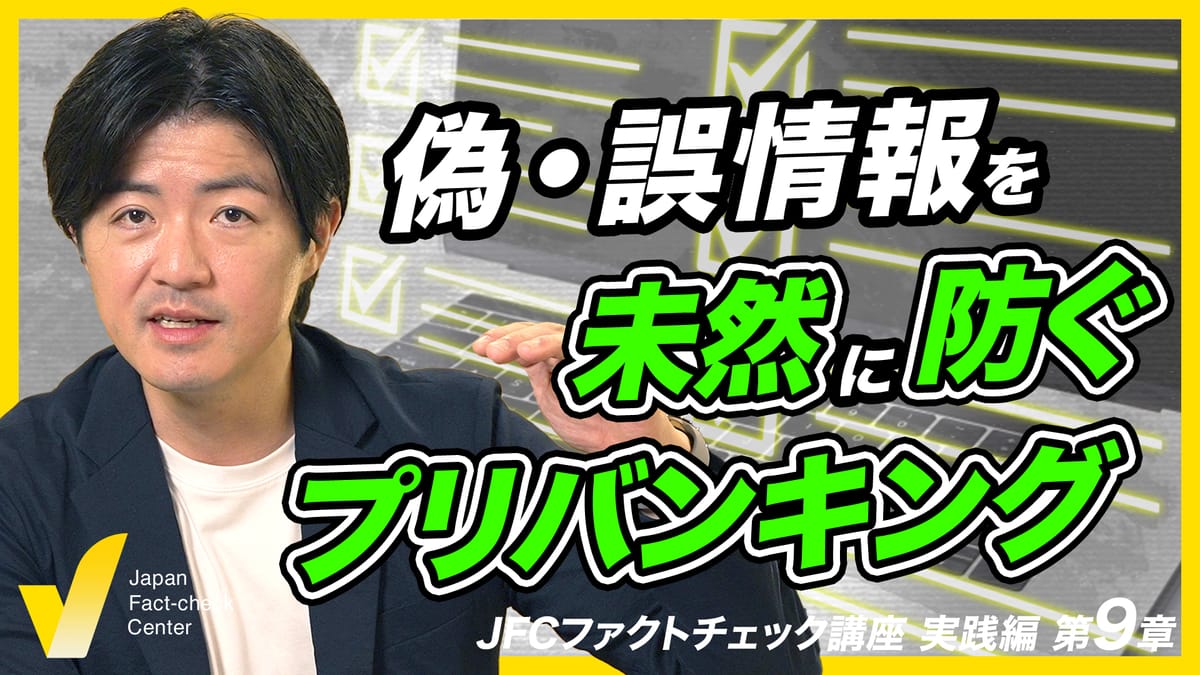
日本ファクトチェックセンター(JFC)のファクトチェック講座です。
実践編第8回は、よく質問されるファクトチェックと調査報道や裏取りとの違いについてでした。第9回は世界のファクトチェック事例や新手法を解説します。
(本編は動画でご覧ください。この記事は概要をまとめています)
ファクトチェックの多様な事例
ファクトチェックには原則がありますが、同時に、検証対象の選び方や組織のあり方などは多様です。国内外の事例を紹介します。
Factchek.org
ファクトチェック団体としては老舗のFactchek.orgはアメリカ政治に関する偽情報に対応するために、「有権者のための消費者保護センター」を目指して2003年に設立されました。
そのため、主なトピックに並ぶのは「バイデン大統領」「トランプ前大統領」、そして「その他の大統領候補」などアメリカ政治中心です(2024年7月27日現在)。
例えば、「バイデンが不法移民に家賃を支払っているという根拠のない主張」という記事には、見出しに検証対象と検証結果=根拠なしが記され、記事内では検証過程が詳細に記述されています。
Snopes
同じく老舗のSnopesは1994年設立。元々は都市伝説の検証から始まりました。現在は政治経済関連の検証もしますが、むしろ、エンタメ系の話題のファクトチェックが目立ちます。
例えば、「チャップリンは自分自身のそっくりさん大会で負けたことがある?」「スタローンはデニーロが“意識高い系”だからと共演を断った?」などの検証などがあります。
ファクトチェックといえば、政治的・経済的な話題の検証を思い浮かべる人も多いですが、著名人に関する噂話もファンから見れば切実で身近な話題であり、広く拡散します。そのため、公共性を持ちうる話題です。
大手メディアのファクトチェック
The Washington Post
ワシントン・ポストには政治面にファクトチェッカーという特設ページがあり、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証も得ています。
IFCNの諮問委員の一人でもあるグレン・ケスラー記者を中心に主に政治家の発言を検証し、嘘の代名詞であるピノキオの数で信憑性を判定しています。
IFCN認証を受けたその他の大手メディア
世界3大通信社のAP、AFP、ロイターはいずれもIFCN認証を受けており、それぞれにファクトチェックの特設ページを持っています。
一方で、IFCNの認証を受けずに、独自に情報の検証に取り組む大手メディアも存在します。
BBCの調査報道的なファクトチェック
イギリスの公共メディアBBCも情報の検証に熱心に取り組んでいます。ただし、IFCNの認証は受けておらず、特設ページの名前はBBC Verifyです。
ページを見ると「ウクライナ戦争:NATOの兵士がウクライナで戦っているというロシアの主張をファクトチェック」という風に、IFCNの原則に則った形の一般的なファクトチェック記事もあります。
一方で「ガザの給水施設の半数が損傷または破壊 BBC衛星データで明らかに」という風にデータを駆使した調査報道もあります。
真偽が不確かな状況や言説に対し、データに基づいて客観的な事実を伝えることがBBC Verifyの役割で、ファクトチェックはそのための手法の一つです。
NHKの特設ページ
日本の公共メディアNHKには「フェイク対策」と銘打ったページがあり、こちらで検証記事を積極的に配信しています。
BBCと同様にIFCN認証はありませんが地震などの災害や選挙など、偽・誤情報が広がった際には、様々な検証記事や解説記事などを公開しています。
記事中に検証過程の説明が少なく、根拠へのリンクなどがないために「ファクトチェック」とは呼びにくいですが、偽・誤情報の問題が日本で広く知られる上で大きな力となっています。
科学的な検証のために
医療健康や気候変動など、偽・誤情報が拡散する分野の多くに科学が関係し、検証には科学者の協力が不可欠です。
そのため、世界のファクトチェック団体の中には、科学者が参加していたり、緊密に協力したりしている団体もあります。
カナダのL’Agence Science-Presseは科学専門メディアで、科学が関係するファクトチェックに取り組んでいます。フランスのScience Feedbackは気候変動や医療健康に関する言説を科学的に検証しています。
偽・誤情報を予防する「プレバンキング」
ファクトチェックはすでに拡散した情報の真偽を検証します。それに対して、近年より効果が高いと注目を集めているのが「プレバンキング」と言われる手法です。
「プリ・プレ」で「事前に」、つまり、拡散が予想される偽情報・誤情報に対して、あらかじめ検証・解説する記事を出すことを言います。
JFCでも2023年7月に福島第一原発からの処理水の海洋放出について、偽・誤情報が拡散しそうなポイントを予測し、まとめて検証して解説する記事を出しました。
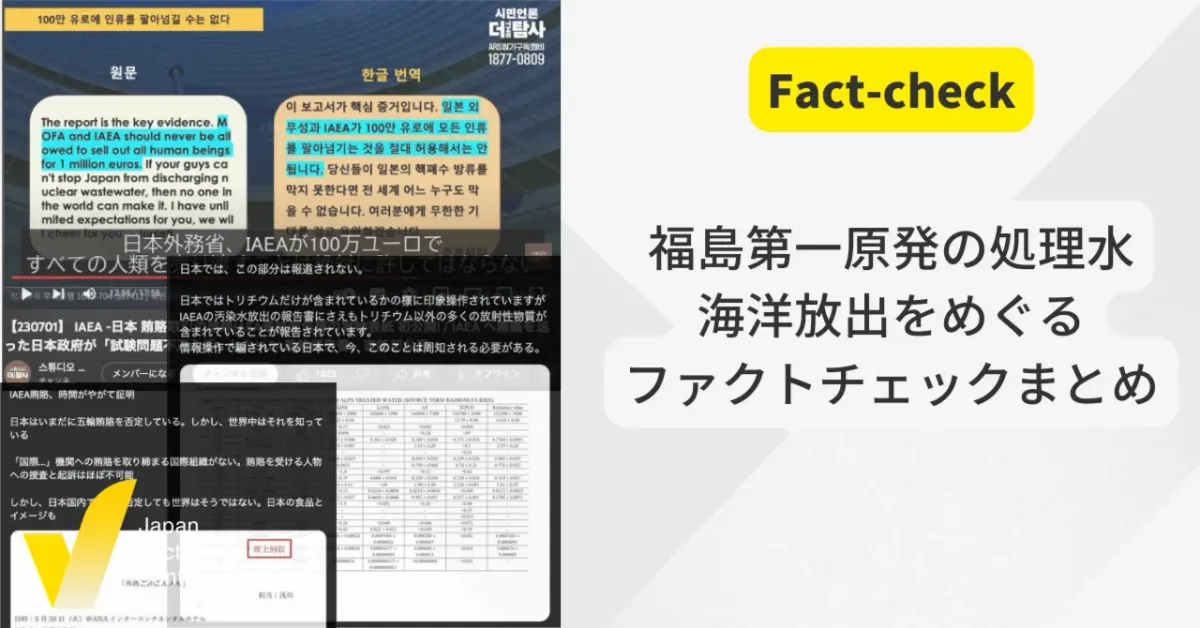
処理水をめぐっては、海洋放出の方針が固まる前後から、偽・誤情報の拡散が始まっていました。ただ、その時点では検証をしようにも直接的な関係者である東京電力や日本政府などの資料がほとんどでした。
JFCでは国際原子力機関(IAEA)が中国など他国の専門家も参加した報告書が出た段階でそれらの資料をもとに今後拡散しそうな偽・誤情報のポイントをまとめて検証しました。
「情報の空白」に対応する
偽・誤情報が拡散する理由の一つとして、気になる情報をネットで探したときに、信頼性の高い情報が見つからなくて、たまたま目にした信頼性の低い情報をそうとは知らずに信じてしまう、ということがあります。
これを「情報の空白」とか「データの空白」と言います。
その話題を検索する人が増える前に、事実に基づいた信頼性の高い情報が検索結果に出てくるようにする。プリバンキングは情報の空白を埋める作業です。
そして、ファクトチェック自体にも「情報の空白」を埋める効果があります。偽・誤情報が拡散してから、その拡散を検知し、検証をして、記事をまとめ、配信する。それまでの間には、必ずタイムラグがあります。ファクトチェックの効果が低いのではないかと指摘されるポイントの一つです。
しかし、検索結果を見てみましょう。多くの偽・誤情報はSNSで拡散します。スピードは非常に早いですが、一過性で、検索結果の上位にはほとんど残りません。それに対して、ファクトチェック記事が公開されていれば、検索で出てきます。
そうすると、その偽・誤情報が再び拡散したときに、気になった人が検索すると、証拠に基づいて検証した記事を目にすることになります。これも「情報の空白」を埋める作業と呼べるでしょう。
次回はさらなる偽・誤情報対策へ
ここまでファクトチェックを理論と実践の両面から解説してきました。最終回となる20本目の次回は、ファクトチェックだけではない、偽・誤情報対策の広がりについて説明します。
アンケートにご協力を
動画を見た方は、ぜひ簡単なアンケートにご協力ください。 https://forms.gle/QdVa9A5v3RDnfBW59

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。
毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。