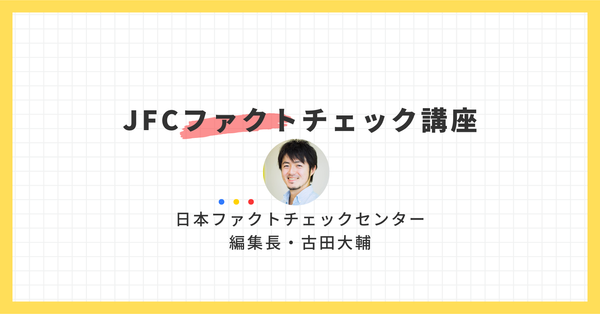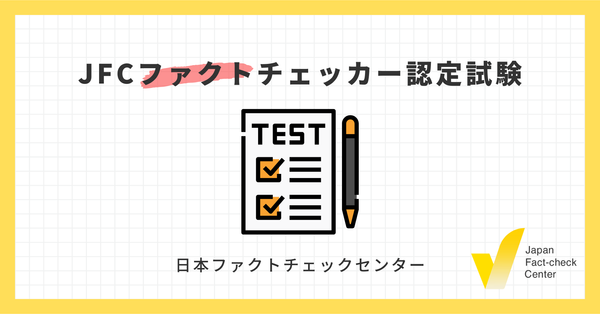日本の党首討論がライブ検証されないのはなぜ 選挙に関する日米台のファクトチェック比較【解説】

総選挙が始まりました。10月15日の公示から27日の投開票日まで、わずか12日間の短期決戦です。各メディアなどで党首討論が相次いで実施されましたが、アメリカなどで見られる発言のライブ検証はありませんでした。日本と他国のファクトチェックや偽・誤情報の傾向の違いを解説します。
米大統領選のファクトチェック
民主党のカマラ・ハリス副大統領と共和党のドナルド・トランプ前大統領の2候補が争うアメリカ大統領選。候補者が直接対決する恒例のテレビ討論会は9月10日夜(現地時間)に実施され、大手メディアやファクトチェック機関が2人の発言を細かく検証した。いくつかの事例を並べてみる。
Fact-checking Kamala Harris and Donald Trump's 1st presidential debate (ABC)
Fact-checking the presidential debate between Trump and Harris (NBC)
Fact checking debate claims from Trump and Harris' 2024 presidential faceoff (CBS)
NPR fact-checked the Harris-Trump presidential debate. Here's what we found (NPR)
Fact check: Donald Trump, Kamala Harris debate on ABC News (CNN)
世界的な注目を集める選挙だけに英BBCなども独自にファクトチェックをしていた。これらのファクトチェックからは、トランプ氏の発言に誤りが非常に多かったことがわかる。
トランプ発言の多くに明確な誤り
米候補者討論会で両者の発言を55箇所も検証したワシントン・ポストのファクトチェック記事「Fact-checking 55 suspect claims, mostly Trump’s, in debate with Harris」を見てみよう。
明確な誤りや一部が誤りなどと判定されたのは、トランプ氏が36箇所、ハリス氏が7箇所あった(筆者=古田が集計)。細かく見ると、ハリス氏へは「一部が間違い」「印象操作」「古い話」などの判定が並ぶ一方で、トランプ氏へは「すでに何度も否定されている」「馬鹿げた中傷」「まったく根拠がない」など、より強い言葉で誤りを指摘している。
ワシントン・ポストの記事を書いたのはベテランのファクトチェッカーとして知られるグレン・ケスラー記者だ。彼がトランプ氏に厳しく、ハリス氏に甘く検証しているのか。実際の発言とケスラー記者の検証の概要を並べてみる。
まずはトランプ氏の検証された発言:
「私達が経験しているインフレは、ほとんど誰も見たことがないものだ。おそらく、我が国史上最悪のインフレだ」=誤り。インフレ率は2022年に9%まで上昇したが、現在は3%を下回る。1980年は12.5%、1979年は13.3%、1946年は18.1%。
「私たちの国には、刑務所や拘置所や精神病院から何百万人もの人々が流入している」=まったく根拠がない。
「私はわが国史上、最も偉大な経済のひとつを作り上げた。最高の経済だった」=誤り。GDPや失業率などの指標を比較すると、トランプ政権が最高とは言えない。
次にハリス氏の検証された発言:
「エコノミストたちは、トランプ氏の消費税は中流家庭に年間約4000ドルの負担増になると言っている」=高い見積もりの可能性。3900ドルやそれ以上という専門家もいるが、それより低い見積もりもある。
「私は2020年に、採掘を禁止するつもりはないと明言した。私はアメリカの副大統領として、採掘を禁止したことはありません」=印象操作。2020年の大統領選のときにハリス氏は採掘に反対の立場だった。
「彼(トランプ氏)がプーチンについて『やりたい放題やればいい』と言い、プーチンがウクライナに攻め入ったのは有名な話だ」=部分的な誤り。トランプ氏はこの文脈で「やりたい放題やればいい」と言ったわけではない。
これらの検証を見ると、ハリス氏の誤りも具体的に指摘していることがわかる。冒頭で紹介した他メディアのファクトチェックも同様だ。ハリス氏の間違いを指摘する部分もあるが、トランプ氏の発言の誤りをより多く指摘している。
英メディアのガーディアンに至っては「トランプ氏の主張の検証」と題してその誤りを焦点をファクトチェックしている。
台湾総統選のファクトチェックは
2024年1月に投開票された台湾の総統選はどうか。台湾ファクトチェックセンターは候補者討論会をリアルタイムで検証した。3人の候補者発言を合計23箇所にわたって検証している。
_2.png?itok=nF0SJVsz)
23の検証のうち、7つは発言を「正確」と判定した。残りの16は「データは一致しているが推論が単純化しすぎ」「データは一致しているが部分的な情報しか得られない」「重要な前提や事実が隠されている」「一部が確認したデータと一致しない」などと不正確な点を指摘している。
しかし、アメリカにおけるトランプ氏のように「まったく根拠がない」というような判定は見当たらない。むしろ、ハリス氏への検証と同じように、一部に間違いや不正確な部分があるという指摘が主だ。
日本の党首討論は
一方で日本。総選挙をめぐる党首討論会が相次いで実施されたが、10月19日現在、日本ファクトチェックセンター(JFC)を含めて主だったメディアやファクトチェック団体から党首発言に関する検証記事は出ていない。今後出てくる可能性はあるが、アメリカや台湾とは対照的だ。
ファクトチェック分野で、日本はもともと出遅れていた。国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証を受けた団体が日本で最初に誕生したのは2023年。わずか1年前のことだ。アメリカではIFCN認証がない大手メディアもファクトチェックを実践しているが、日本での事例は少ない。
JFCもIFCN認証を受けている団体の一つだ。総選挙に関しては10月19日までに14本の検証や解説の記事を出した。しかし、党首討論に関しては、検証記事を出していない。
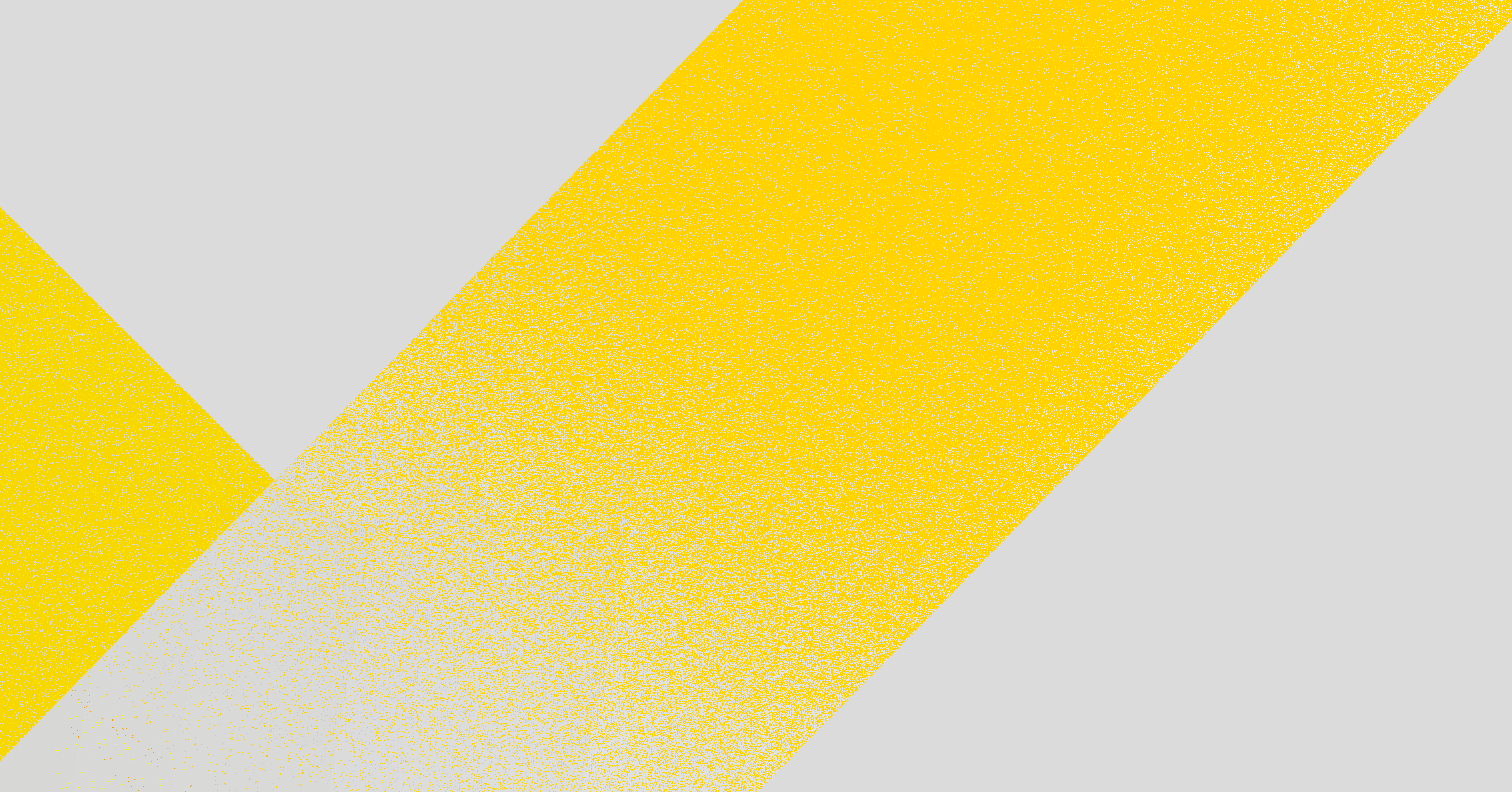
筆者(古田)は複数の党首討論会を文字起こしして内容を精査した。事前に研究機関にも相談をし、疑わしい主張があれば検証をする準備は進めていた。だが、党首の発言には、ファクトチェックの対象となりうる「客観的に検証可能な事実」で、疑わしいと思える箇所が少なかった。
ニコニコニュースで配信された【衆院選2024】ネット党首討論を例に見てみる。自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党、共産党、国民民主党、れいわ新選組、社民党、参政党の9党首が参加し、1時間20分にわたって経済政策と憲法改正について議論した。
テレビ各局の党首討論よりも時間が長く、日本記者クラブでの党首討論よりも党首間でお互いに質問と回答を交わす機会は多かった。しかし、9党首全員に発言機会を与えるために、発言時間が1回につき60秒か30秒と短く区切られていた。
これは他メディアなどの党首討論でも同じ傾向だ。アメリカの討論会は2人、台湾は3人なのに比べて、日本は登壇者が多すぎるために発言の多くは自分たちの政策の概要にとどまり、他者への質問や回答も深く掘り下げていく時間的な余裕がない。
お互いがポイントを絞って、自分たちの政策のアピールを優先させる場において、わざわざ明らかに事実と異なる発言をすることは合理的とは思えない。ハリス氏や台湾総統選の3候補の発言に大きな間違いが少ないのはそういう理由だろう。
むしろ、トランプ氏のように公然と誤った発言を繰り返す方が例外的とも言える。
法解釈の違いは検証対象になるか
党首討論の質疑の中には、他党の党首の発言が誤っているのではないかと指摘する点もある。
ニコニコの討論で言えば、共産党委員長の田村智子氏と社民党党首の福島みずほ氏が、2015年9月に成立した安全保障関連法について、集団的自衛権の行使を容認し、アメリカとともに戦争することを可能にするもので「憲法違反だ」と主張した。
これに対し、自民党総裁の石破茂氏と公明党代表の石井啓一氏は「(集団的自衛権を)ごく限定的に認めている」(石破氏)、「憲法9条の専守防衛の範囲内」(石井氏)と反論した。
この議論の片方を「正確」、もう片方を「誤り」と検証できるのか。ファクトチェッカーの間でも意見は分かれるかもしれない。筆者(古田)は法律や憲法の解釈や評価について、客観的な事実に基づいて判定を下すような検証は難しいと判断した。
朝日新聞は2024年の立憲民主党代表選で、候補者だった枝野幸男氏の安保関連法に関する「個別的自衛権の範囲で十分に読み込める」という発言をファクトチェックし、「根拠不明」と判定している。
これに対し、一橋大院法学研究科教授の市原麻衣子氏が「憲法および個別的自衛権概念に関する解釈論の領域に入ってしまっている」と指摘し、「ファクトチェック記事として出すことに違和感を覚える」とコメントした。
市原氏はJFCの運営委員でもある。この件に関して議論をしたことはないが、筆者(古田)は市原氏と同じ意見だ。朝日新聞の取材を受けた枝野氏自身も「法解釈における『見解』の違いであり、『ファクト』の正誤とは全く別次元」と述べている。
ファクトチェックの対象とは
ファクトチェックは「事実の検証」であり、オピニオン(意見)の検証ではない(JFC「ファクトチェックとは」「ファクトチェック指針」)。
「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持とう」と発言する人がいたとして、検証ができるのは「雲が出ている」という発言部分だ。「雨が降りそうだ」という推測や「傘を持とう」という判断は、その人の自由。「雲が出ている」という部分だけが客観的に検証が可能だからだ。
JFCが総選挙に関して10月19日までに出した14本の検証・解説記事はこの原則に則っている。候補者の発言が改変されていたり、各党の公約について事実と異なる情報が拡散したりした事例を検証した。いずれも客観的に検証可能だった。
党首や著名候補者の発言には誤りがない、ということではない。党首討論のような場よりも発言量が多くなる選挙演説などでは、より間違った発言が出る可能性は高くなる。
JFCは引き続き、候補者の発言にも注目している。
更新
更新1
この記事を公開した翌日の10月21日に共同通信が党首討論会をファクトチェックした記事を配信しました。
「ファクトチェック 終末期医療見直しと尊厳死法制化 医療費抑制にはつながらない 根強くはびこる誤解 共同通信編集委員 内田泰」という見出しで、10月12日に開かれた日本記者クラブ主催の7党首討論会での国民民主党の玉木雄一郎代表の発言を検証しています。
検証対象は「われわれは高齢者医療、特に終末期医療の見直しに踏み込んだ。尊厳死の法制化も含めて。こういったことも含めて医療給付を抑えて若い人の社会保険料を抑える」という発言。
2005年の厚生労働省の調査データで医療費全体に占める死亡1ヶ月前の費用は3%に過ぎないというデータを挙げて「終末期医療を見直しても医療費は大して抑制できない」と指摘しています。
「誤り」「不正確」などの判定は出していません(10月25日更新)。
更新2
選挙の党首討論会ではないですが、10月9日の国会での党首討論に関して、早稲田大瀬川ゼミが運営するウェブメディア「Wasegg」が石破首相の発言をファクトチェックし、10月25日に公開しています。
「【ファクトチェック】石破首相「(地震対応の)補正予算成立には2カ月はかかる」は不正確 国会党首討論で発言」という見出しで、検証対象は「(能登半島地震について)補正予算成立には2ヶ月かかる」という石破首相の発言。
阪神淡路大震災や熊本地震は約1ヶ月で補正予算が成立していることから「不正確」と判定しています(10月25日更新)。
判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。
毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。