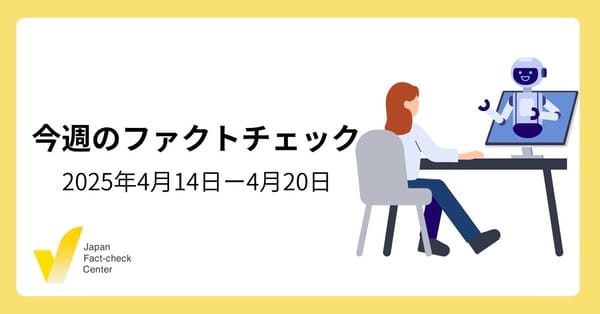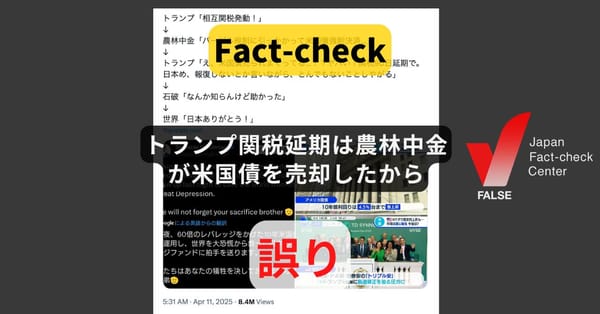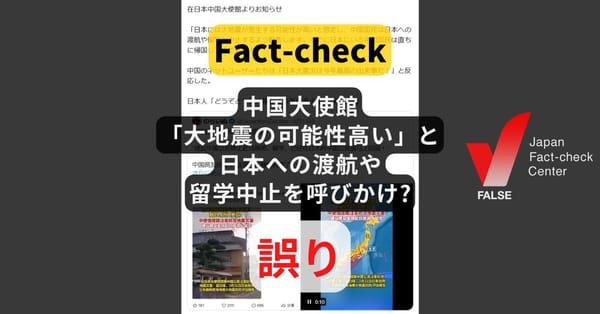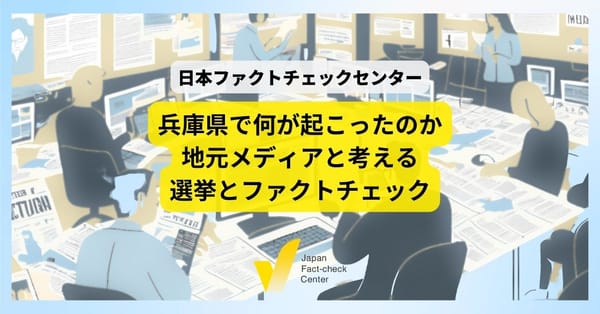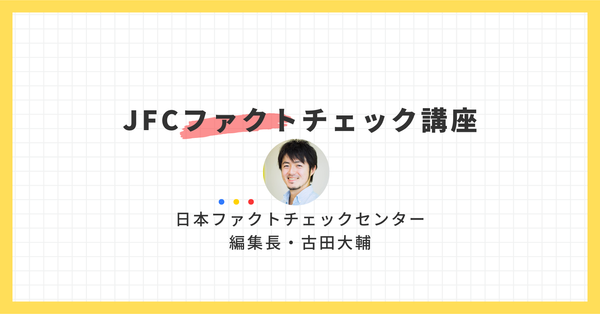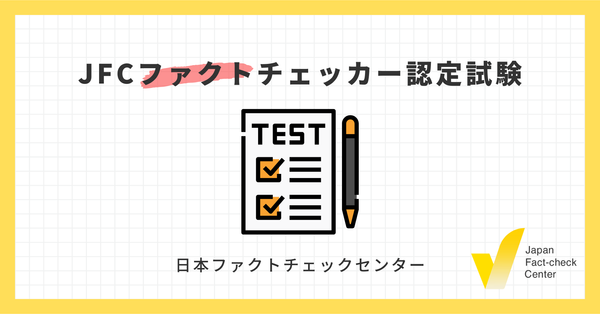偽・誤情報対策に不可欠な「社会全体での取り組み」と「情報的健康」【情報インテグリティ】

4月2日の国際ファクトチェックデーに合わせ、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)/日本ファクトチェックセンター(JFC)が開催した情報インテグリティシンポジウム。この記事ではパネル討論2「調和のある情報空間を目指す総合的な対策」の内容をお届けします。
モデレーター:古田大輔(日本ファクトチェックセンター 編集長)
パネリスト:
・山本龍彦氏(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
・桒原響子氏(公益財団法人日本国際問題研究所研究員)
・吉田弘毅氏(総務省情報流通振興課企画官)
調和のある情報空間を目指す総合的な対策【パネル討論2】
登壇者の自己紹介
古田:山本さんから一言ずつ自己紹介をよろしくお願いします。
山本:皆さんこんにちは。慶應義塾大学のロースクールで憲法学を教えております山本と申します。今お話にあったように憲法学が専門なんですけれども、主にテクノロジーと人権、テクノロジーと民主主義の関係について考えてまいりました。
その関係で総務省さんのデジタル関連の検討会などにも巻き込まれている状況です。あとで吉田さんからもご紹介がありますが、総合的なICTリテラシーを進める「デジタルポジティブアクション」という会合があり、そちらの会長も務めております。
もう一つ、デジタル時代に我々の尊厳、つまり「ディグニティ」が本当に実現されているのか、我々は本当にハッピーになっているのか、ということを根源的に問うセンターを慶應義塾で立ち上げました。クロスディグニティセンターというもので、いろんな領域がクロスする中で人間の尊厳がどうあるべきか。哲学や歴史学、法学、さらには理系の知見も含めて検討する領域横断型の研究拠点の共同代表を務めております。
その中で「アテンション・エコノミー」と「情報的健康」というテーマのプロジェクトも立ち上げ、そちらのリードも務めております。
今日は後ほど、情報的健康、つまりこの時代に情報をバランスよく摂取する、自分が摂取している情報がどこから来ていて誰が作っていて、どれくらいの“添加物”が含まれているのか──これはあくまで比喩=アナロジーですが──そういったことを考え、情報的な意味での健康体をつくることが、偽情報などへの「免疫」となり、最終的には自分のハッピーにつながるのではないかと考えております。
古田:「情報的健康」というのは「情報インテグリティ」とも非常に関連性があると思うので、また後ほど詳しく伺いたいと思います。
古田:それでは桒原さん、お願いします。
桒原:日本国際問題研究所研究員の桒原と申します。よろしくお願いいたします。
私はですね、古田さんとは日本でも、アメリカでも、国際会議でご一緒する機会があるご縁なのですが、日本のシンクタンクで活動しながら、海外──具体的にはカナダのオタワにあるマクドナルド・ローリエというシンクタンクでも、偽情報対策の研究活動を行っています。
もともと私は国際政治の分野で情報発信やコミュニケーションの研究をしていたのですが、世界的に──先ほど最初のパネルの最後に古田さんがおっしゃっていましたけれども──2016年のアメリカ大統領選挙が“ウェイクアップコール”となり、偽情報対策や誤情報対策が始まったという流れがありました。
その時、日本は全く反応できていなかったんですね。そこに問題意識を持ちました。当時は偽情報に関する研究自体が日本ではできなかったので拠点をカナダに移して、対策が進んでいるNATO諸国、G7諸国の一員でもあるカナダで研究活動を行っています。
現在は東京も拠点としながら、国内外の政府をはじめ、民間セクターやシビルソサエティなど、あらゆるアクターの方々と一緒に、偽情報対策・偽情報研究の分野で活動しています。
古田:日本は対策の進んだ国から学ぶことが多いと思いますので、また後ほど詳しくお話を伺えればと思います。それでは吉田さん、お願いします。
吉田:はい、総務省で誹謗中傷対策などを担当しています吉田孝樹と申します。
総務省では、誹謗中傷などの権利侵害情報、いわゆる闇バイトの募集のような違法情報、有害情報などを含む、偽情報・誤情報に対する政策の立案や法制度の整備・運営を行っています。
この後にご説明申し上げますが、大きく3本柱で取り組んでいます。1つ目は制度面、たとえばSNSなどの情報プラットフォームを運営する企業に関する法制度の運用や改正などです。2つ目は技術の開発。そして3つ目が、先ほど山本先生にも会長を務めていただいている官民連携の意識啓発活動であるデジタルポジティブアクションです。
この制度面の取組の中でも、「偽情報・誤情報が流通しないようにするにはどうすればよいか」「広告の観点から何ができるのか」といった幅広い視点から検討を進めています。
私自身は、これまで東南アジアでの勤務や、サイバーセキュリティ分野など情報・テレコム領域を長く担当してきました。そうした知見を生かしつつ、社会課題の解決を図り、かつ表現の自由もきちんと確保できるように、何ができるかということに取り組んでいます。
ちなみに私個人のフィルターバブル対策としては、SNSアカウントが暗いニュースや偽情報を調べてばかりいると汚れてきたので、毎日寝る前に柴犬の動画を10分間見て、フィルターバブルから逃れて情報的・精神的健康の向上を図っています。本日はよろしくお願いいたします。
総務省の3本柱「普及啓発」「技術的対応」「制度的対応」
古田:偽情報・誤情報対策に関わる人たちの「精神的健康」って、本当に国際会議でも話題になるぐらい重要な問題なんですよね。僕自身も本当に悩んでいるんですが。それでは今、吉田さんから触れていただいた対策の中身について、より詳しくご紹介いただければと思います。
吉田:はい、今、1枚のスライドがスクリーンに映っていると思います。これは「総務省の取り組みでどういったことをしているか」をまとめたものです。スライドの上部、オレンジ色の枠にはこれまでの経緯が書かれていて、左側の緑の箱には、現在進めている6つの柱があります。そのうちの3つを詳しく説明します。
まず経緯ですが、総務省では一昨年から「デジタル空間における情報流通の健全性確保に関する在り方に関する検討会」を始め、昨年9月にその取りまとめを公表しました。その中で総合的な対策をやりましょう、多様な関係者の連携が重要であるといった提言を行い、それに基づいて政策を進めています。
その実際のところが左側に6つの柱が示されています。
1つ目は「普及啓発・リテラシー向上」です。2つ目は「人材の確保・育成」。3つ目は「ファクトチェック」。ファクトチェックに関しては政府が何かをするというより、社会全体でファクトチェックが普及するために何ができるのかを議論しました。社会の中で、古田さんが編集長をされている日本ファクトチェックセンターのような取組が進むことは良いことですし、社会の中で様々なファクトチェック団体によるファクトチェックが進むことが素晴らしいと考えています。
4つ目は「技術の開発・実証」。これは後ほど説明します。5つ目は「国際的な連携・協力」。例えば、一昨年のインターネットガバナンスフォーラム(IGF)は京都で開催されましたが、国際的なディスカッションも行われていますし、偽・誤情報は2国間の協議でも大きな話題になっています。6つ目は「制度的な対応」です。
この6本の柱の中で、総務省が政策として頑張っているのはこの赤色の3つです。「普及啓発・リテラシー向上」に関しては、今まさに、右側にある「デジタルポジティブアクション」という官民連携の意識啓発のプロジェクトを進めているところです。登壇している山本先生を会長に、参加企業として、Google、LINE、Meta、TikTok、X(旧Twitter)などのプラットフォーマーをはじめ、通信事業者、NewsPicks、スマートニュースなどのキュレーションをしている方にも参加いただき、社会全体での取り組みを目指しています。
「デジタルポジティブアクション」の中で、実際やっている取組は3つです。1つ目は「世代に対応した普及啓発」、セミナーや教材づくりや広報活動です。2つ目はSNSなどデジタルサービスにおける「サービス設計上の工夫」です。たとえばニュースサイトでは書き込み欄に利用者が「こんなニュースくだらない」とか「バカだ」とか書こうとすると「そういうことを書いていいですか?」というサジェスチョンを表示するなど、誹謗中傷の発生を抑えるような設計の工夫があり、そのような取組を行う事業者さんの背中を押しています。
3つ目は「信頼性の高い情報がちゃんと表示される工夫の背中を押す取り組み」です。例えば、災害時に信頼できるメディアの情報が表示順位が上がってくるとか、こういう偽・誤情報に気をつけようと表示するとか、選挙のときにはニュース配信が優先的に表示されるよう各企業・プラットフォームでも行われているところを促していこうというものです。
「普及啓発」「サービス設計上の工夫」「表示の工夫」の3つを進めながら、リテラシー向上をみんなで図っていこうというのがデジタルポジティブアクションです。
スライドの真ん中にあるのが「技術開発・実証」です。偽・誤情報を検知する技術は、それによって開発した企業が劇的に儲かるものではありません。サイバーセキュリティのような情報資産をまもることによって企業利益に大きく影響するものでもないので放っておいては技術が大きく進展・普及することは難しいと考えています。
そこで政府が支援して技術開発を支援したり、AI生成画像をマッピングで可視化する技術の開発支援などをしています。また、出ている画像のチェックをするだけではいたちごっこになるため、発信者が誰かをしっかりと確認できる技術の支援もしています。これは〇〇新聞でつくった記事だとはっきりしていれば、その新聞の信頼度を考えて参考にできます。情報発信者の真正性・信頼性の技術支援ですね。
最後の制度的対応ですが「情報流通プラットフォーム対処法(プラ法)」の改正があり、今年の4月1日から施行されています。これは、ネット上の違法・有害情報に対応するため、大規模プラットフォーム事業者に対して、対応の迅速化、運用の透明化、窓口表示の義務化などを求めるものです。
もう一つ、デジタル広告の分野でも取組を進めています。偽情報の流通の背景にはただの愉快犯もいると思いますが、それによってお金が儲かる人もいます。それをどう対応するかを考えていて、一番下の②で書いてある偽・誤情報を配信している媒体に広告が広告主が意図せず配信されてしまうことがあるため、広告配信の際には意識してくださいと注意喚起をしながら、ガイダンスを策定して本日4月2日14時からパブリックコメントを開始したところです。
こうした「普及啓発」「技術的対応」「制度的対応」の3本柱を通じて、総務省としては、偽・誤情報や権利侵害情報などへの対策を推進しています。
古田:先ほど紹介した情報インテグリティ調査の中で「差別表現や誹謗中傷への方策としてどのような方法が望ましいか?」という質問をしました。その回答で最も多かったのが「国による法的規制(52.3%)」でした。次に「啓蒙活動(46%)」、その次が「デジタルプラットフォーマーによる監視と対応」でした。
これは制度上の取り組みにも関係してくる話かと思います。「国による法的規制」への期待について、どのようにお考えでしょうか? この点については、表現の自由との関係も含めて、後ほど山本さんにもお話しいただきたいのですが、まずは吉田さん、いかがでしょうか。
吉田:さまざまな情報──偽情報・誤情報に限らず──課題が発生したとき、「政府として何かすべきではないか」という声が必ず出てきます。しかし、政府が対応すべき対象とは何か、それが明確であること。そして政府が取る手段が適切で他に悪影響を及ぼさない形であることが重要です。
たとえば誹謗中傷に関しては、何が誹謗中傷にあたるかは最終的には訴訟などを通じて判断されますが、そういう面では対応ができうるものです。偽情報・誤情報となると、かなり難しい。ある人にとっては偽情報と思える内容でも、他の人にとってはそうではない場合もあります。
どういう明確な制度を考えるか難しくなります。「できること」と「できないこと」があり、権利侵害情報や違法情報ではない、偽・誤情報に関しては制度的対応の検討は慎重に進める必要があると考えています。
モデレーションで重要な「足し算の対応」
古田:山本さんはいかがお考えでしょうか?
山本:「制度的対応」にはいろいろな形があります。たとえば、モデレーションを求めるもの。削除を要請するような「引き算の対応」も含まれます。逆に、信頼できる情報を目立つ形で表示し、そういった情報の流通を活発にするような、「足し算の対応」もあります。
また、どちらかというと後者だと考えていますが、情報摂取に関するユーザーの合理的判断を助けるような情報、たとえばレコメンダーシステムのロジックなどですが、そういった情報を開示させるような法制度も考えられます。透明性を高めていくような法的な規律ですね。
偽情報や誹謗中傷の問題の根底には「アテンション・エコノミー」というビジネスモデルがあると思います。私たちの「時間」や「アテンション」、たとえば「PV」「いいね数」「エンゲージメント時間」などが広告に売られ、それによって私たちは無料で利用できている。
その構造の中では、どうしても刺激的でアテンションを引きやすいものがアルゴリズム上で優位に表示され、拡散、増幅しやすくなる傾向がある。そのためモデレーションの「削る」対応には限界があると私は思います。
それに加えて、表現の自由とのバッティングもありますし、削除だけに依存すれば「モグラ叩き」状態となる。構造自体が変わらない限り、次々に“モグラ”が現れる──そのような状況になってしまいます。
ですので、「足し算」のための政策、たとえばプロミネントですね。現状も、選挙時には政見放送のような情報をプッシュする政策が取られている。しかし、多くの人がテレビを見なくなってしまった今、政見放送にどれだけ意味があるのか、こういった情報のプッシュをデジタルの世界にどう移していくのか考える必要があるかもしれません。
透明性を高めて、特定のプラットフォーム企業についてはアルゴリズム挙動に関するデータを開放させ、研究者がそれを調べる。ジャーナリズムとして、こうしたアルゴリズムを監視することも重要になってくるでしょう。
そうやって透明性を高めることで、ユーザー自身が「このプラットフォームはどうだろう。依存症にさせて私たちの情報的健康を奪っているのでは」と問い、別のところに移るとか市場の圧力を高める構造を作っていく。
削るということは、特定のものについては確かに必要かもしれませんけど、それは最小限。吉田さんがおっしゃった通り、抑制的に考える必要があると思います。他方で後者の方は積極的に考える必要があると思います。
消費者の判断を後押しする「情報的健康」
古田:「ユーザーがこの情報は健康か不健康かを選び取る」という点に関して、「情報的健康」という概念について改めてここでご説明いただけたらと思います。
山本:誰かが「この情報は健康、不健康」と一方的に決めてしまうと、それは全体主義的な非常に怖い世界になってしまいます。ですから、私たち情報的健康プロジェクトのメンバーは、そうしたことは全く考えていません。
食の世界で例えるならば「これは健康に良いから食べなさい」と強制されるのではなく、食品表示法のように「この食品には何が入っていて、どこで誰が作っているのか」が開示されていて、それを見て消費者が自分でこれを食べるのはやめようとか、最終的に自分が判断する。
同じように、情報についてもメタ情報──たとえば、オリジネータープロファイルとかC2PAとか「情報の来歴」を明らかにするようなメタ情報をつけていく動きがあります。
こうした表示によって、ユーザーが「今自分はどういう情報を摂取しているのか」「偏っていないか」と気づけるようになり、最終的に、ダイエット中にラーメンを食べるのを控えるように、「今日は、この刺激的なサムネイルのコンテンツは見ないでおこう」と合理的な情報摂取をしていくようになる。それが情報的健康の考え方です。
古田:日々ファクトチェックをしていて感じるのは、政治系のまとめサイトなどで、ほとんどが誤りだと判定できる情報ばかりにもかかわらず、ものすごくシェアされているということです。
ソーシャルリスニングツールで見ていると、新聞社のコンテンツよりも何十倍もまとめサイトの記事がシェアされていることがよくある。SNS上で同じような人たちが何度も何度も拡散している。
やはり子どもの頃から成分表示的に、どこから来た情報で、どういったリスクがあるのか”ということを教育する必要があると強く感じます。ここまでの話を踏まえて「総合的な取り組み」という観点から、桒原さんにもご意見をいただけますか?
偽・誤情報対策に欠かせない「社会全体」での取り組み
桒原:お二人の専門家のお話を踏まえたうえで、私からは「総合的な対策」についてお話しさせていただきます。
総合的な取り組みで海外でよく言われる欧米や台湾もそうですけれども「Whole-of-society(ホールオブサティ)」という考え方があるんです。日本語で直訳してみると「社会全体」です。
偽情報・誤情報対策は基本的に政府だけでは不可能という認識のもと、政府だけでなくて民間セクター、メディア、市民社会団体などが協力してインフォメーションエコシステムーー情報的健康という話がありましたがーーに介入していくことで、情報エコシステムをよりヘルシーにしていくというアプローチが取られています。
欧米もそうですし、台湾でも、どこの国も地域も完璧にできているわけではないですが、これが必要だという考え方に則ってアプローチをやっているんです。
日本ではWhole-of-societyアプローチという考え方が欧米、台湾と比較してかなり低いと言わざるを得ない状況です。
分かりやすいように今の日本のアプローチのイメージをスライドにしました。1つずつ説明をしたいと思います。
まず政府が何をやってるか。情報収集分析が行われていて、それに基づいてカウンターナラティブ、どういうナラティブを情報空間で発信していくのかという検討を行っています。それに基づいて情報発信あるいは戦略的コミュニケーションなどと言われる発信のアプローチがあります。
総務省さんが取り組まれているようなリテラシー向上のための啓発活動ですとか制度作りといったアプローチもある。また国際協力などが行われています。
それに対してプライベートセクター/メディア、そしてシビルソサエティという風に書いてありますけれど、これらの活動に関しては古田さんの日本ファクトチェックセンターのように活動とプレゼンスを増やしていく団体もこの数年の間で増えているのは日本の特徴だと思うのですが、他のアクターに関しては比較的活動規模が小さいですし、アクターの数もそもそも少ないと思います。
プライベートセクター/メディアの方からどういうことをやってるかを説明したいと思います。これはメディアに特化していると思うんですけれども信頼される情報源の構築ですね。また、ファクトチェックを行っているメディアもあります。
新しい企業も立ち上がって、これがOSINTと呼ばれる情報分析を行う企業も出てきました。また偽情報、プロパガンダ検知のシステム開発を行うような企業もあります。サービス提供もそうですし、SNSプラットフォーム企業を中心としてコンテンツモデレーションなどを始め、コンテンツ管理を行っているという状況です。
その一方でシビルソサエティ、研究機関ですとか、古田さんのファクトチェック機関もそうですし、あらゆるえ非政府団体がありますが、これらの団体はファクトチェック活動を始め、質的量的分析、それに基づく情報発信、コミュニティ・ネットワーク形成などを国内外で行っているという
状況です。なぜ日本でWhole-of-societyアプローチの考え方が進まないのか。色々理由があると思うんですけれども、第一に、1つ目のパネルでも指摘がありましたが、偽情報に対する認識が構築されきっていない。日本では比較的、偽情報による深刻な被害を受けた事例も少なかったこともあり、他国と比較して社会全体で感度はそれほど高くないのだということです。それゆえにアクターが少ない。
そうした中、2022年末に日本では「国家安全保障戦略」が出ました。ここに外国からの偽情報の拡散を含む情報に日本として対処していくことが初めて盛り込まれた。これが先に出てしまっているので対策が、政府がメインになっているということがあると思います。
古田:僕のイメージもこの図に非常に近いです。シビルソサエティ側の人間として、自分への反省も込めて、忸怩たる思いがあります。
世界のファクトチェック団体の多くは2017〜2020年頃、つまり2016年の米大統領選を受けて一斉に立ち上がりました。でも、日本ファクトチェックセンターの設立は2022年、社会全体でこれはまずいという話になったのは2024年。プライベートセクターや市民社会の動きが遅れる中で、政府主導で対応が進んでいるのが現状です。
吉田さん、この図を見て、どのようにお感じになりますか?
民や市民社会のエコシステムをどう作るか
吉田:おっしゃる通りで、官・民・市民社会それぞれが発展していくことが一番好ましいと思っています。
様々な課題ごとに政府がという話が出てきますけれども、官・民・市民社会が均等に取り組みが多くなるのが、理想の姿です。それをするためにそれぞれの中でエコシステムができることが大事です。
例えば技術開発の施策においても、偽・誤情報の検知技術も政府がお金を出して研究開発をしても、その後に社会実装が進まないと意味がない。実装しないと意味がないんですけども、そういうコミュニティとエコシステムがまだ出来上がりきってないと考えてます。
だから、プライベートセクターやメディア、シビルソサエティの中でエコシステムができるために政府がどう働きかけるかを考える必要があるとこの図を見て思いました。
古田:技術支援って大変だと思うんです。アメリカやイギリスのツールは、世界中に利用者がいてビジネスとしても成り立つ。でも、日本発の技術が同じようにグローバル展開できるかというと、現実的には難しい。
もう1つ、海外にはGoogleやMetaのようなグローバル企業が資金提供して開発している事例がありますが、その枠に日本の企業や技術が選ばれるのかというと、これもハードルが高い。政府としても本当に大変だろうと思います。
山本さん、そうした中で、学術的な立場から「情報的健康」や「Whole-of-Society的なアプローチ」をどう広げていくべきとお考えでしょうか?
「デジタルポジティブアクション」で官・民・市民社会をつなぐ
山本:「情報的健康」という概念を提唱した背景には、まさにこのシビルソサエティをどう後押しできるかという観点がありました。
「偽情報に気をつけましょう」とスローガン的に叫んでもなかなか伝わらない。対策に関する用語は、アテンション・エコノミーやフィルターバブル、エコーチェンバーなど横文字ばかりで、子どもや高齢者には伝わりにくい。だからこそ、食とのアナロジーを用いて、いま起きている状況を体感的に知っていただきたいというのがありました。
また、この官・民・市民社会の3つをつなぐという意味で、総務省の「デジタルポジティブアクション」は、1つの場となると思っています。現在、リテラシー教材がいろいろ作られていますが、何を参照していよいかわからないという声も聞かれます。
ですので、それぞれ特色を整理し、マッピングをしていこうとか、よいものを積極的に評価してアワードなどを設けようなどと検討しており、市民社会の方を巻き込みながら総合的にリテラシーを高める工夫をしていこうとしています。
ガバメントの役割ですが、そういう場を設定する役割があると思います。それとパネル1で神戸新聞の永田さんも話していましたが、やはりメディアの役割は重要です。SNSやアルゴリズムが何をしているかを監視し、報道していくことがこの3つを繋いでいく役割を果たすのではないかと考えています。
古田:情報インテグリティというのは、もともと国連が中心になって推進している概念です。その国連の提言の中でも、報道機関やジャーナリズムが果たす役割は非常に重要視されています。
民主主義国家において、信頼できる情報を発信するのが政府だけになってしまうと、それは全体主義的な匂いがしてくる。だからこそ、独立した複数の自由な報道機関による情報発信というのが不可欠です。
さて、まとめに入る前に、桒原さんにお伺いしたいのですが、日本のこの現状──つまり、ホール・オブ・ソサエティ・アプローチが不十分であるという状況に対して、カナダなど他国ではどう対応しているのか、参考になる事例を教えていただけますか?
政府が「運転」するのは不思議ではないけれど
桒原:他国の事例も含めて日本の足りないところに触れたいと思います。たくさんあるんですが、時間も限られているので、3つに絞ってご紹介します。
第1に、先ほども申し上げました国家安保戦略があります。今日のシンポジウムは非常にバランスが取れた会議になっているのであまりこれに触れる方がいらっしゃらなかったんですけれども、実は外国からの脅威という文脈で偽情報が語られる場合が多い。
国家安保戦略があるため仕方ないことなのかもしれませんが、日本の偽情報や災害の歴史などを見れば、外からの脅威かあるいは国内発の偽情報かというと、時代を問わず、コミュニケーションの手段を問わず、圧倒的に国内発の情報が多かったはずです。
海外からの脅威と偽情報という関係では、日本は言語障壁、日本語という特殊な言語があるので比較的他国の社会と比べてレジリエントだというような認識もあります。ただこれに関してはAI技術がここまで発展しているので、この言語障壁は突破されたと思って備えるべきです。
様々な専門家の方々がもうすでに取り上げられていますけれども、偽情報をより身近なリスクとして捉えていくべきだという風に思っています。
第2に、カナダをはじめ他国と比較して日本で明らかに課題だと感じるのが量的分析への投資が極端に少ない点です。AIドリブンリサーチと言われますが、カナダやドイツもそうですけれども、データサイエンティストが偽情報対策の根換に関わる、あるいはデータ分析のために政府が予算をつける。こういった動きが目立ちます。
情報空間あるいは社会の情報エコシステムの問題点はどこにあるのか。脆弱なオーディエンスがどこにいるのか。論争を呼びやすいトピックスがどこにあるのか。そうした基礎的な分析ができていないと根拠ある対策ができないからなんです。ここを日本はもっと促進していくべきなんだろうと私は理解しています。
第3に、対策をどう回していくか。先ほどからも話題になってる通り、多様なアクターの動員。これが欠かせないことになりますが、日本ではこれは圧倒的に足りないです。政府がメインアクターというのは実はカナダでもそうなんです。
車に例えると、偽情報対策において政府がドライバーズシートに座っているというのは全く不思議なことではなくて、いろんな国でそうなんです。ただ、車の製造や運転に関わっているアクターが多様ではないところに日本の課題があります。
偽情報対策というのは政府だけではできません。互いの足りないところ、手をつけられないところを補え合えるコラボレーションを多面的に、セクターを超えて行っていくことしかないと思うんです。
例えばシビルサエティに関しては当然資金面での支援が必要であるし、また研究分野では共同研究も考えられます。どういう事例があったのか、どういう情報を自分たちは持っているのかを共有をし合うことも重要ですし、リテラシー教育や情報発信も当然強化されなければならない。
様々なセクターを超えて効率的にかつ効果的にやっていくことができるような社会全体のアプローチを目指していくと、欧米あるいは先進的な偽情報対策を行っている社会に近づけていけると考えています。
古田:僕も同感で、偽情報は「より身近なリスク」として語る必要があると思っています。ただ、ここ数年の世界的な潮流を見ると、むしろ逆方向に進みかねない懸念もあります。背景にあるのがトランプ政権です。
私はこの10年ぐらい、ジャーナリズムやファクトチェックのいろんな国際会議に出ています。そこで2016年以降に語られていたのは、偽情報がヘイトスピーチが氾濫する中で、民主主義社会をどう維持できるか、人権をどう守れるかという危機意識です。
ところが、トランプ政権によって話が逆転した。例えば、「ファクトチェックは言論の自由に対する抑圧であり、民主主義的ではない」というような主張が出ています。ヴァンス副大統領がミュンヘンの安全保障会議で欧州に向けて語ったのはまさにそういう発言でした。
このような流れも理解したうえで、どう対策を進めていくか。最後にまとめをお一人ずつお願いします。
政府だけではできない
吉田:Whole-of-societyプローチをどうやっていくのかが非常に大事です。政府だけではできない。そういう中でこういうフォーラムのような場でみなさんとディスカッションし、最初の発表のように現状がどうか情報を共有し、状況が把握し、意見交換していくことが重要だと思います。
一身独立して一国独立するという言葉もありますが、各個人のリテラシーをどこまで上げていくと日本としてうまくいくのか。その目標をガバメント、プライベートセクター、シビルソサエティと共有し、ディスカッションしながら制度、技術、リテラシーの取り組みを連携して進めていきたいと思っています。古田:ありがとうございます。続いて桒原さん、お願いします。
プロアクティブ、中長期的なアプローチを
桒原:はい。これまでの偽情報対策というのは「情報空間から悪意あるコンテンツやアクターを排除する」という、防御的なアプローチが中心だったと思います。
今後は、より先制的で「情報の空白」を埋めるプロアクティブなアプローチ--プレバンキングという言い方をしますけれど--これも必要になってくる。中長期的なアプローチを目指していく必要があります。
他方でトランプ政権の影響もあり、偽情報対策が米国だけでなく世界の至る所で崩壊し始めている状況で、日本はどうしていかなければならないか。
国際協力でより信頼ができるロングラスティングなパートナーを見つけておくことも重要ですし、対策の先にどういう未来が待っているのかを先をいく国々の事例を見つつ対策を進めていく。そういった敏感さや柔軟性も必要だろうと考えます。
ありがとうございました。
古田:ありがとうございます。山本さん、お願いします。
アテンション・エコノミーという「構造」を変えていく
山本:偽・誤情報を生み出す構造に目を向ける時期に来ていると思っています。
「アテンション・エコノミー」というのは民主主義にとっては非常に手強いビジネスモデルで、我々の欲とか動物的な情動的な部分に強く働きかけるところがあります。なかなか我々が理性で抗いがたいところがある。
食欲で考えると、すごく好きなものが目の前にあればどうしても食べたくなってしまう。けれども、我々はリテラシーによって「今日はやめておこう」と思えるようになった。夜中にカロリーの高いものを食べればある種の後ろめたさを感じるようにもなりました。
そういう意味で、「食欲」への衝動については、それを過度に利用しないという社会規範が形成され、我々も偏食や食べすぎに気を付けるようになった。ですから、「情報欲」についても、リテラシーを諦めてはいけないと思っています。それによって我々の意識が変わっていくことが、今のアテンション・エコノミーをめぐる競争のあり方を変える。
いかに刺激をしてアテンションを得るかという競争--「刺激の競争」と呼んだりしますが--、内容や説得力よりもいかに情動的な部分にトリガーをかけられるかという競争から、いかに善良なアルゴリズムを使っているかという競争になっていく必要がある。
そのために透明性や我々の意識変化がどうしても必要で、それによって構造を揺さぶっていくことが重要で、研究も進めていきたいと思っております。ありがとうございました。
コラボが苦手な日本社会 民主主義を守るために協力を
古田:ありがとうございます。山本さんたちが提唱する「情報的健康」も、総務省が取り組む多様な施策も、結局は一人では成り立たないし、Whole-of-societyアプローチは実現できません。
今回、日本ファクトチェックセンターが電通総研さんと一緒に共同調査をし、今回、慶應義塾大グローバルリサーチインスティテュートさんとこのシンポジウムを共催し、様々な所属や背景を持つ方々に登壇いただいたのは、社会全体でのアプローチを広げるためでもあります。
残念なことに、日本はコラボレーションが苦手な社会です。組織の論理、所属の壁、同じ業界でも会社が違えば競争相手となりがち。
フィリピンにはメディアやファクトチェック機関や専門機関が協力する素晴らしいコラボレーションのプロジェクトがあります。担当者に質問したことがあります。
「日本だと例えば新聞業界の中でも競争が激しくて協調が難しいのに、どうやって業界も超えたコラボができるの?」
彼女はこう言っていました。
「フィリピンだってもちろん競争は激しい。だけど、偽・誤情報の問題に関しては協力して戦わないと民主主義が壊れてしまう。民主主義を守るために協力しなきゃいけない」
日本でも、今回の2024年の“気づき”をきっかけに、この高い壁を超えて協調と連携が進んでいくことを願っています。本日はどうもありがとうございました。
アーカイブ動画とシンポジウム記事
情報インテグリティシンポ2025 パネル討論2
情報インテグリティシンポ2025
基調講演1: 情報インテグリティ調査の概要
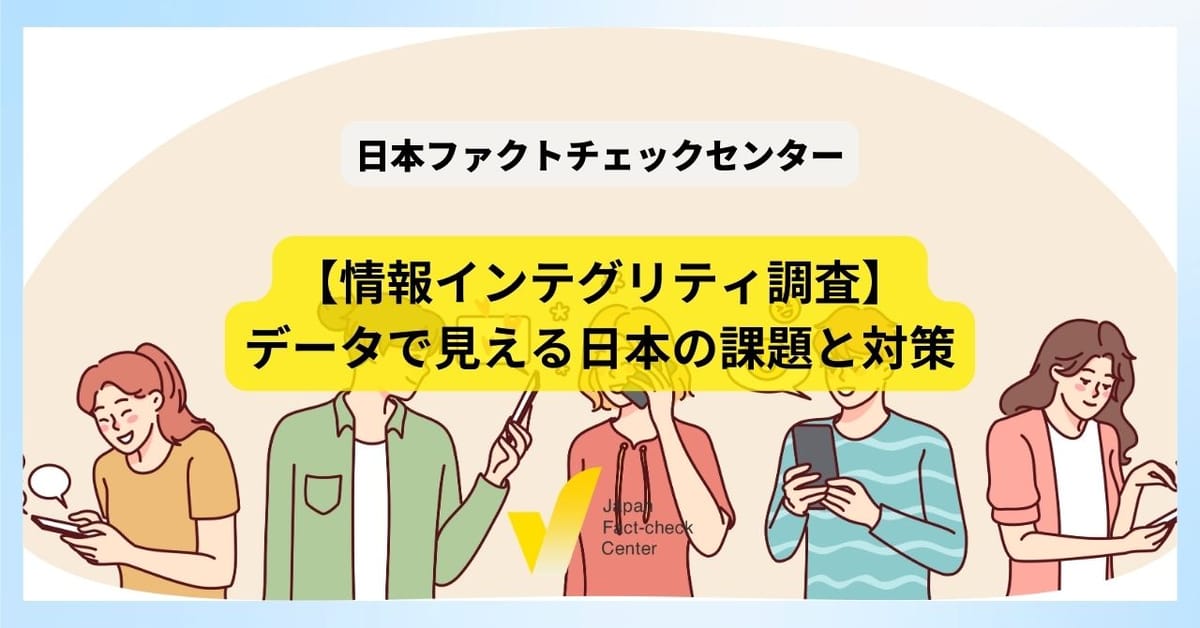
基調講演2: ファクトチェックとメディアリテラシーの現状と展望
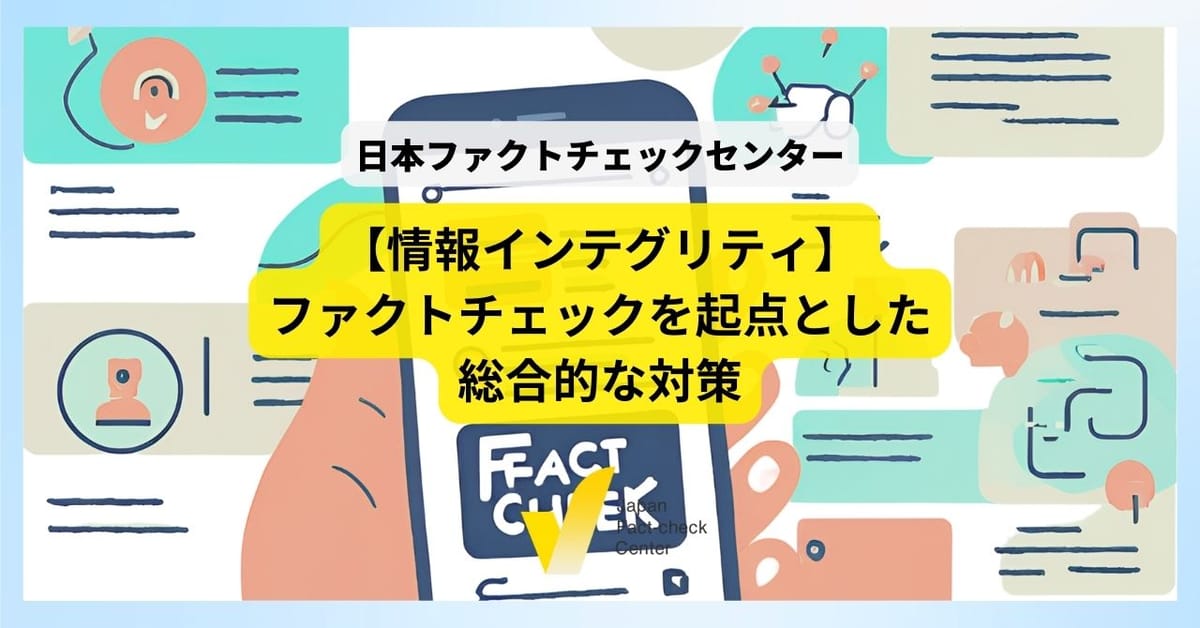
パネル討論1: 選挙とファクトチェック
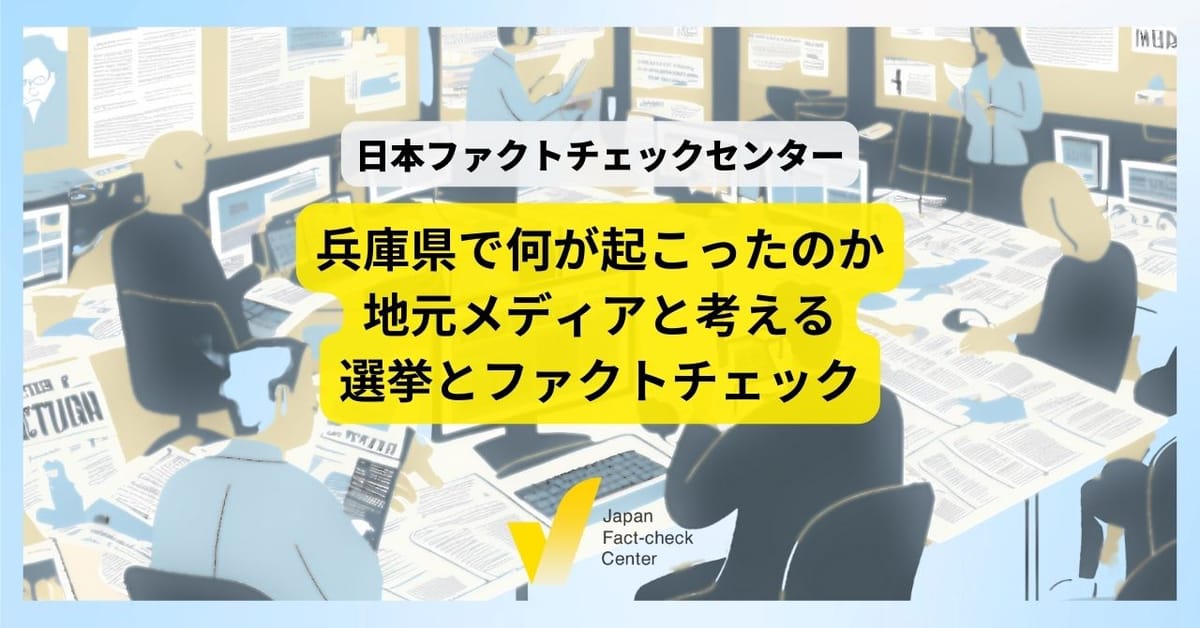
判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。
毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。