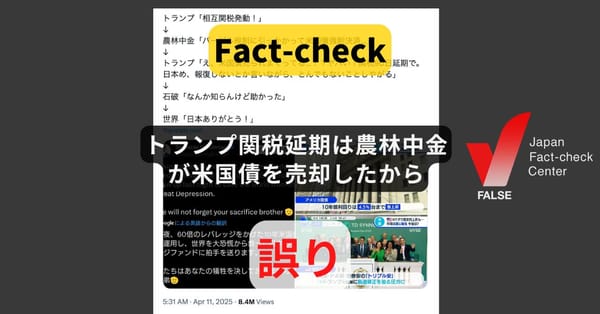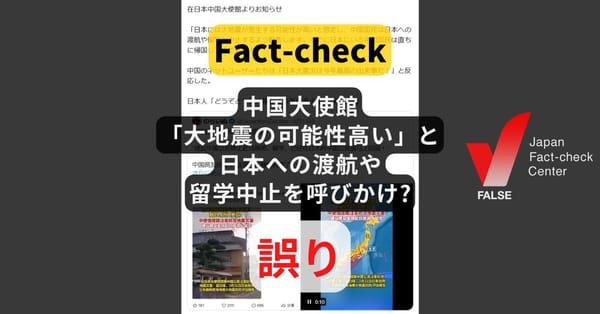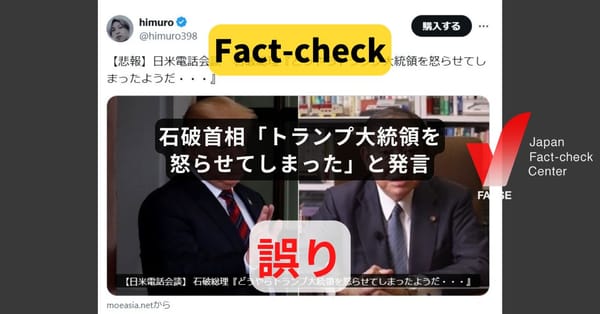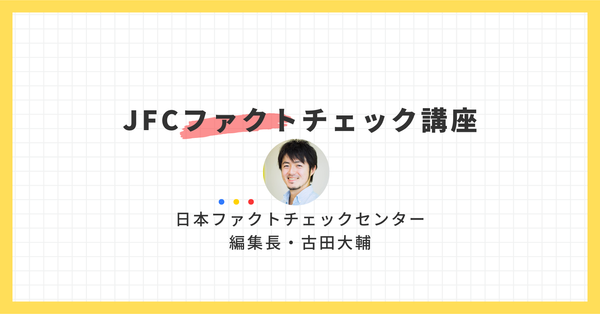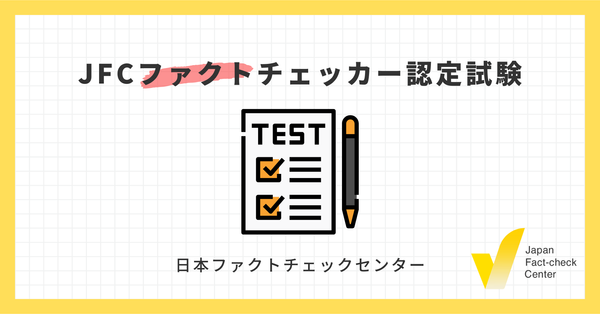兵庫県知事選から考える選挙とファクトチェック 「情報の空白」をいかに埋めるか【情報インテグリティ】
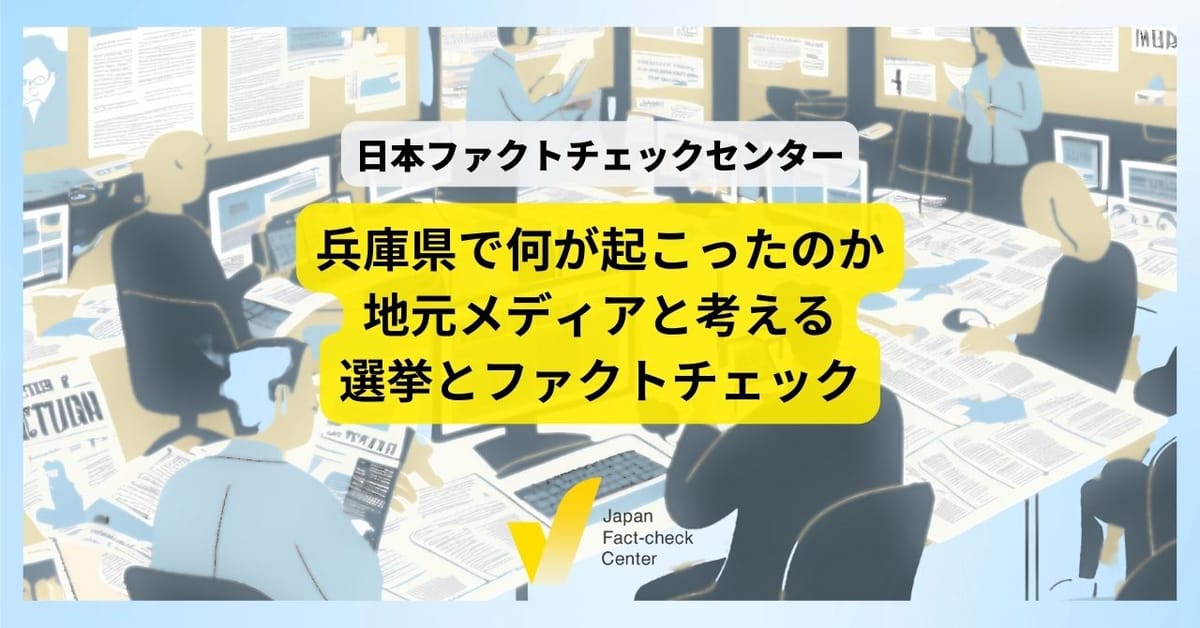
4月2日の国際ファクトチェックデーに合わせ、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)/日本ファクトチェックセンター(JFC)が開催した情報インテグリティシンポジウム。この記事ではパネル討論1「選挙と情報インテグリティ」の内容をお届けします。
モデレーター:古田大輔(日本ファクトチェックセンター 編集長)
パネリスト:
・澁谷遊野 氏(東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授)
・永田憲亮 氏(神戸新聞社編集局報道部次長)
・西村 健吾氏(TikTok Japan 公共政策本部 公共政策部長)
選挙と情報インテグリティ【パネル討論1】
登壇者の自己紹介
古田:モデレーターを務めます古田です。よろしくお願いいたします。まず最初に、登壇者の皆さまにご自身がどのように情報インテグリティの分野に関わっているか、自己紹介をお願いしたいと思います。
澁谷:澁谷と申します。東京大学大学院情報学環で准教授をしております。私は偽情報やデジタル空間の情報データに関しまして、主にデータ解析の観点から研究に取り組んでおります。
2つの観点から取り組んでおりまして、1つ目は大規模なデジタル空間のデータを解析することによって、偽情報を含めた様々な情報がどのように流通し、影響を与えているのかを研究しています。
2つ目は、大規模なオンライン実験や調査を通じて、ユーザーがどのように情報を信じてしまうのか、どのような情報を受け取っているのか、どのようなインターベンション(介入)が効果を持つ可能性があるのかを研究しています。
最近の事例では、能登半島地震の際の情報、著名人のなりすましによる投資広告詐欺、生成AIによって作られたコンテンツの消費状況などについて調査研究を行っています。
永田:神戸新聞社の永田と申します。
私は兵庫県にある神戸新聞社から参りました。現在、報道部に所属し、行政担当のデスクとして、政治や行政の取材を担当しています。その関係で、昨年11月の兵庫県知事選や、昨年春以来続いている告発文書問題などを担当してまいりました。
今日のテーマである「選挙と情報インテグリティ」に関連して言いますと、まさにSNS型選挙という形で、これまでの選挙取材・選挙報道のやり方が全く通用せず、受け身に回らざるを得なかった。
今日は「受け身に回ったことの反省」や「失敗から得られた教訓」などをお話しできればと思っております。
西村:TikTok Japanで公共政策本部 公共政策部長を務めております、西村健と申します。私は主に政策形成や制度運用の分野に携わっておりまして、政府機関や国会議員の方々と連携しながら、さまざまな政策課題への対応を進める役割を担っております。
最近では「闇バイト」の勧誘やなりすましによる投資詐欺といった問題が社会的にも注目されており、総務省や警察庁、自民党などと議論を重ねてきました。
私自身は、新卒で国土交通省に入省し、12年間勤務しました。その後、外資系企業やコンサルティング会社を経て、現在に至ります。官と民の橋渡しができればいいなと思っています。
TikTokは使ったことがある方も多いと思いますが、縦型動画を中心としたプラットフォームです。現在、日本国内のユーザーは約3,300万人と非常にメジャーになっています。
ライブ配信も行っており、閲覧だけではなく、海外ではライブコマースやeコマースへも拡大しているプラットフォームになっております。
古田:早速、討論に入っていきたいと思います。
まず、皆さんも注目していたと思いますが、兵庫県の知事選について、先ほど永田さんからも少しお話がありました。実際にあのとき何が起こっていたのか、そしてそこから得た教訓についてお話しいただければと思います。
斎藤知事が大逆転した兵庫県知事選、そのとき神戸新聞は
永田:兵庫県知事選は17日間の選挙戦でしたが、嵐のようでした。信じられないほど、偽情報、誤情報、真偽不明の情報、デマ、誹謗中傷が拡散していくという選挙でした。
それに対して、先ほども申し上げましたが、既存の報道機関がネット空間の沸騰状態にうまく入り込めず、対応の仕方がわからないまま終わってしまった。そんな状況でした。
皆さんもご存知かもしれませんが、「既得権益」「オールドメディア」「斎藤さんを引きずり降ろそうとしている」「テレビは真相を隠している」などの情報が跋扈していました。
報道機関の立場としては、現場で取材していた記者個人の名前や顔がネット上で晒され、攻撃の対象になるという状況も発生しました。
何より、ソーシャルメディアが投票行動、さらには選挙結果に決定的な影響を与える。そういう選挙だったと感じています。
選挙結果にソーシャルメディア、ネット空間がどの程度影響をあたえたのかを考える一助になると思って3枚ほどスライドを持ってきました。
1つ目は「データで見る兵庫県知事選」というシリーズの一部です。これは選挙が終わった直後から神戸新聞で始めた取り組みですが、立花孝志さんのYouTube動画の再生回数を調べたものです。選挙期間中に立花さんの動画は 1,700万回 見られていました。
当選した斎藤元彦知事の動画再生数は 80万回 ほどです。単純に比較すると、立花さんの動画は斎藤さんの 20倍以上 見られていたということになります。
さらに、この立花さんの動画を拡散していたアカウントが10個前後あって、これらがものすごく拡散していた。確実な裏は取れていませんが、その中には収益目的と見られるものもあったと考えています。
次は、私たちがJX通信社と共同で行った情勢調査の結果を紹介します。「投票行動の参考にしたメディアは何か?」と聞きました。
まず、111万票とって当選した斎藤元彦さんに投票した、あるいは投票しようと考えていたと答えた方々においては、YouTubeやX(旧Twitter)などを参考にした人の割合が高い という傾向が見られました。
2番手だった稲村和美さん、尼崎市の元市長で96万票取りましたが、その支持者層では、テレビや新聞といった既存の報道機関を参考にした という人が多くいました。
つまり、接するメディアによって動向が違うことがわかりました。
ここから言えるのは、SNSや動画投稿サイトにどれだけ浸透できるかによって、投票行動が左右されてしまうということを肌で感じました。
最後のスライドです。知事選の結果としては、最終的に斎藤さんが勝利しましたが、実は10月頃までは稲村さんが圧倒的にリードしていました。それをネットの盛り上がりで斎藤さんが猛追して抜き去った。
このスライドの左下にあるグラフを見ていただくと、告示前の10月13〜14日時点では稲村さんが ダブルスコア で斎藤さんを上回っていたことがわかります。
ところが、告示後の11月3〜4日ごろから急激に斎藤さんの支持が伸び、11月14〜15日、つまり投票日の約2〜3日前にはほぼ並んだ状態になり、その後は一気に逆転していったのです。これほどわかりやすい調査は珍しいなと思います。
また、右側のスライドには、SNS上で拡散された主な言葉が並んでいます。「既得権益」「テレビは真実を隠している」といった言葉や、全くのデマである「稲村候補は外国人参政権に賛成している」など、センセーショナルで事実に基づかない言説が大きく広まりました。
インフルエンサーがいるような選挙では、ネット空間にいかに「取材に基づいた裏付けのある情報」を届けていけるかが大きな課題であり、これが今回の教訓だと感じています。
古田:私も選挙後に神戸新聞社さんの勉強会に参加させていただきましたが、ショックだったのは、記者の方々がご家族や友人からも「今まで嘘を流していたのか」と疑われたという話でした。
これは神戸新聞社さんがたまたまターゲットになっただけで、どの報道機関でも起こりうることだと感じました。
澁谷さんに伺います。先ほど永田さんからも、立花さんのアカウントが1,700万回視聴されたという話がありました。ご専門の立場から、こうしたソーシャルメディア上の情報をどう捉えていらっしゃいますか?
YouTubeで園芸系、投資系の一般ユーザーまで選挙に参入 見られていたのは長尺動画
澁谷:私たちの方でも今回、動画が非常に多く視聴されていたという報道もありましたので、YouTubeのデータを分析しました。
その結果、大きく3つの特徴が見えてきました。
1つ目は、言うまでもないかもしれませんが、非常にエンタメ性を意識したコンテンツやサムネイルが多く、閲覧数が伸びるような賛否両論がある内容とかセンセーショナルな内容が非常に多く、一般ユーザーも含めて投稿していました。
具体的には斎藤氏に注目した内容で「マスコミが一切報道しない」とか「地上波より面白い」といった文言が非常に多く使われた動画が多数見られました。
2つ目は、ある意味で意外だったのですが、ショート動画はそれほど見られていなかったという点です。若者の関心が高まったという背景もあり、我々もショート動画が主流だと予想していたのですが、実際には閲覧数で言うと長尺の動画の方がしっかりと見られていたという傾向が見られました。
よく考えてみるとこれはその通りかなと思うのですが、基調講演でもあった通り「情報の空白」で、伝統メディアで摂取できないような情報をユーザーが能動的に自分はこれが知りたいという意識を持って長い動画をしっかり見る傾向があったのではないかと考えています。
3つ目の特徴は、伝統メディアのアカウントの再生数が極めて少なかった ということです。伝統メディアは選挙期間中はある程度、候補者を平等に扱ったり、同じぐらいの時間で紹介するといったようなことが通常だと思いますが、YouTubeでの再生数が多い動画では特定の候補者に着目したものがほとんどです。
これらのアカウントの中には、著名人だけでなく、一般ユーザー、例えば、選挙前はまったく政治とは無関係のコンテンツ、たとえばガーデニングや投資系の動画を投稿していたアカウントが、選挙期間中だけ突如として政治関連動画を発信しだすといったものもありました。これはおそらく収益を目的にした、あるいはイデオロギー的に支持していたのかもしれません。
著名人だけが着目されがちですが、周りにはたくさん、いろいろな意図をもったユーザーが拡散に貢献していると思っています。
古田:このデータについては私も澁谷さんから直接聞いたとき、非常に意外でした。ショート動画よりも長尺の動画の方が見られていたという点は、確かに考えてみれば、投票行動を真剣に考えている人にとっては自然な流れだとも言えます。
また、YouTuberやTikTokerなどのクリエイターは、コンテンツを作る際にトレンドを確認しますよね。トレンドになっていれば、それに乗っかれば見られる、関連動画に上がるだろうと。レコメンド狙いのコンテンツが、アルゴリズムによって拡散される。その構造そのものが「アテンション・エコノミー」の怖さを物語っていると思います。
この点について、西村さん、TikTokというプラットフォームの立場から、現在の状況をどうお考えでしょうか?
視聴数と広告収益を結びつけないTikTokのビジネスモデル
西村:今、永田さんからも兵庫県知事選の問題点について紹介がありましたが、私としても、大きく2つの課題があったと捉えています。
1つ目は、候補者に対する誹謗中傷や偽情報の拡散。2つ目は、収益化を目的とした動画投稿や切り取り動画の大量拡散です。
まず、1つ目の誹謗中傷や偽情報の拡散についてですが、TikTokの大前提として、我々はミッションとして「Inspire creativity and bring joy(創造性を刺激し、喜びを届ける)」を掲げています。
したがって、安全で安心して使える環境が大前提で、コミュニティガイドラインを設けて、これに沿ってコンテンツを審査しています。
今回の兵庫県知事選に関しても、我々としてはこのガイドラインに基づいた対応をしっかり行ってきたと認識しています。
たとえば、候補者に関する偽情報や陰謀論やゴシップはコミュニティガイドラインの「誤情報」という扱いになります。社外の日本ファクトチェックセンターなどもそうですけれど、社外のファクトチェック機関からの見解なども参考に社内でデータベース化をし、それに基づいて「おすすめフィード」に表示させないなど露出を制限するような適切な措置を講じています。
誹謗中傷についてはもう少しシリアスになって「ハラスメントやいじめ」というコミュニティガイドライン上の違反になります。脅迫やヘイトスピーチといったものは、より厳格な対応を取っています。
2つ目の閲覧数に応じた収益化の問題についてですが、TikTokでは 動画と広告配信が紐づいているわけではありません。つまり、投稿した動画が多くみられ、これに連動した広告も見られることでクリエイターに収入が入るわけではありません。
収益化の仕組みとしてはクリエイター・リワーズ・プログラムというものがあります。これは認定されたクリエイターが収益を得られるというものですが、条件が厳しく設定されています。
たとえば、クリエイティブでオリジナル動画を継続的に制作しているなど、かなり厳しい基準が設定されており、切り取り動画などは対象外となります。
ですので、TikTokにおいては、先ほど指摘されたような「収益目当てで誤情報を拡散する」という行為は、やりにくいプラットフォームにはなっていると考えています。
古田:TikTokでは収益化の仕組みが異なるということで、アテンション・エコノミーとはまた違う論理が働いているというご指摘、非常に興味深いです。
ただ、私たちが普段いろいろなプラットフォームを見ていると、実際にはクロスポストが頻繁に行われています。つまり、YouTubeで収益化を狙った動画がTikTokにもアップされる、そういう現状もあると感じています。
また、私たちファクトチェック機関が直面しているのは、そもそも動画プラットフォームではデータが取得しづらく、調査が非常に難しいという問題です。澁谷さん、データ分析の専門家として、この点についてどのようにご覧になっていますか?
プラットフォームから研究者など第三者へのデータ提供が限られている
澁谷:私は普段、データ解析を主にしている立場として、日々感じていることがあります。
たとえば、DSA(デジタルサービス法)のような法制度がある欧州、それから米国と比べますと、日本はプラットフォーム事業者が研究者など第三者に提供しているデータは限られているというのが現状です。
「今、どんな情報が、どれくらい流通していて、どれだけ需要されているのか」という全体像の把握すら難しいというのが現状です。
偽・誤情報のリスクを特定してプラットフォーム事業者で対応することも必要ですが、関連したデータに確実にアクセスできなければ、どの程度効果があったのかを第三者が精査することが難しいです。そのため、研究機関や外部団体が、偽情報の実態把握や対策の効果検証ができる形でデータ提供が行われることが望ましいと考えています。
また、先ほど「クロスポスト」の話もありましたが、いまの状況では分析がなかなかできていません。プラットフォームごとにデータのフォーマットや種類が違いますので。実際にはYouTubeからX(旧Twitter)、あるいはXからTikTok、さらには日本の場合、掲示板とかあらゆる流れがあります。プラットフォームを超えた情報流通をしっかりと見ていかないといけないと思います。
古田:同じ点について、永田さんにも伺いたいと思います。
これまでソーシャルメディアはあまり取材対象として見られてこなかった中で、知事選をきっかけに「これは取材しなければならない」となった。とはいえ、言ってみれば「門外漢」からのスタートだったと思います。どんな点に難しさを感じましたか?
SNSが視野に入っていなかった 選挙で生じた「情報の空白」
永田:正直、今回の選挙以前は、SNSプラットフォーム上の情報が新聞社の取材対象であるという認識をしっかり持てていなかったと思います。
従来の選挙報道・選挙取材の中に「SNS上の情報を取りに行く・見に行く」といった視点がそもそも存在していませんでした。ですので、そういった分野が得意な記者が個人的に見に行って、なんとかついていくのが現状です。
今現在はどうかと言うと、知事選を経て「さすがにもう無縁ではいられない」という意識が社内にも広がり、複数の記者がSNSや動画投稿サイトを日常的にチェックしています。インターネットの討論番組も頻繁に視聴しています。兵庫県知事選をめぐる問題はいまだに継続中ということもあり、関係者が登場する番組は常に見て、紙面化したりデジタルで速報したりすることが日常動作になってきました。
それから、少し話が変わりますが、先ほど「情報の空白」が最大の反省点だと思っているので、そこについて追加で説明させてください。
新聞など報道機関の立場で、兵庫県知事選もそうでした。告示されるまでは、課題報道、問題提起などしていたわけですけども、告示されると公平性を過度に意識します。
公職選挙法の規定は自由な報道を規制していないんですが、どうしても過度に不偏不党・中立を意識しているということで、誰かに不利になってしまう情報の出し方に敏感であった。
それがテレビや新聞の情報を急激に減少させ、そこをネットの言説で埋め尽くされた。そこが情報の空白で、私たちにとっての最大の反省点でした。
今後は同じ轍を踏まないために、SNSの情報にもしっかり反応し、出すべきものは出していくということだと考えています。
古田:今の永田さんと澁谷さんのお話を踏まえ、今後の選挙を見据えたとき、TikTokとしてはどのような対策を講じていこうと考えているか。 西村さん、お願いします。
ユーザーのリテラシー向上に向けたクリエイターとの協力
西村:選挙に対するSNSの影響力は非常に大きくなっています。海外の事例を振り返ってみると、アメリカ大統領選挙ではトランプ大統領はTikTokを含めてSNSを非常にうまく使っていました。例えば、党大会にインフルエンサーを何人も呼んで、彼らに拡散してもらうという手法も、どちらの党派でもメジャーになり、SNSを使いこなす選挙になっています。
一方で、ルーマニアの大統領選では問題が起こっていました。泡沫候補だと言われていたジォルジェスク氏が、SNSで急激に人気を伸ばして非常に多くの票を得たという事がありました。しかし、それが偽アカウントや海外からの影響があったのではないか、TikTokでもそういうことがあったのではないかという疑惑が出て、結局は憲法裁判所から再選挙への出馬を禁じられるという事態も発生しました。
我々としては、先程申し上げたコミュニティガイドラインに基づいて厳格に対策を行っていましたが、こういった疑惑がでてくるということで、SNSには使い方による功罪両面があると思っています。
そういった中で重要なものとして捉えているのが、ユーザーのリテラシーの向上です。これは古田編集長にも参加いただいたものですが、昨年10月の衆院選の際に、TikTokのクリエイターを招いて選挙の偽・誤情報に惑わされないためにできることというセミナーを開きました。これには山口准教授も出ていただいて、TikTokライブを開催しました。
こちらは今年の2月に開催したもので、こちらも古田編集長や山口准教授に参加いただいて、TikTokのクリエイターを招いてワークショップを開催しました。
これは総務省が進めている、ネットリテラシーを高めようという「デジタル・ポジティブ・アクション」というイニシアティブに賛同したもので、パネル討論2にも参加される総務省の吉田企画官にも出ていただきました。
こういった場でまずクリエイターに、SNS上の偽・誤情報の影響についてよく知ってもらって、クリエイターに動画を作ってもらい、それを一般のユーザーに対して発信していく。
どうしても偽・誤情報の問題は難しくて伝わりづらいのですが、幸いTikTokには優秀なクリエイターがたくさんいるので、クリエイターにうまく「翻訳」してもらってユーザー向けに発信してもらうという方法を試みています。
こういうリテラシーを高めることと同時に、プラットフォーム側でしっかりと審査をする。これが車輪の両軸として機能しています。
古田:世界中のファクトチェック機関がいかにユーザーにコンテンツを届けるかを考えていて、キーワードとなっているのが「インフルエンサーとの協力」「ショート動画の活用」です。TikTokのこういった取り組みはまさにその方向性に沿ったものと言えると思います。
多くの人にリーチするクリエイターの方々に、フィルターバブルやエコーチェンバーの問題について発信してもらわないと、私達ファクトチェック団体や報道機関がいくら記事を書いても、同じような人にしか届かない。私達がこの1年間、情報発信を頑張っても認知度が10%に届かないのは、それを示しています。90%に届けるにはクリエイターの方々の協力、ショート動画の活用が不可欠でしょう。
参院選の話も出ましたが、永田さん、どのような報道をしていきますか。
届けることの重要性、新聞社もYouTubeへ
永田:これからの選挙は有権者の方々が様々なネットの言説に触れて「事実はどうなんだ」となると思います。新聞社の立場で言いますと、取材で裏付けられた確かな事実を連続的に届けていく。
先ほど古田さんおっしゃったように「届けるのが大事」で、自社のサイトであげても見に来てない。ニュース接触はすごく少ないと感じてます。SNS空間にいかに届けていくのか。これは問題点としてはすごくある。
我々新聞社もYouTubeに登場していくことも考えられるのかもしれません。
古田:いかに届けるか。ソーシャルメディア上の拡散を研究される澁谷さんから見たらどういうことが必要とお考えでしょう。
AIが発達する中で信頼性の高い情報をどう届けるか
澁谷:今回のテーマでないんですけど、AIに関連して話したいと思います。
去年ですね。生成AIが非常に使われるようになって、革命的な変化が起こるんじゃないかと言われていました。実際は起きたとは言えないという話もあり、日本だと特に生成AIによる偽動画などはあまり確認されず、多くはなかったというのが現状です。
ただ、それで安心して大丈夫かと思っています。「情報の空白」という話もありましたけれど、伝統メディアに対する信頼やプラットフォーム、デジタル空間における情報に対する信頼とか、短期的な評価ではなく、中長期的な影響、特に青少年への影響を検証していく必要があると思っています。
信頼を壊すのは一瞬、築くのは非常に地道な活動が必要です。生成AIによるいわゆる「ディープフェイク」だけじゃなく、翻訳とか簡単な動画編集とか大量にできるようになってます。誰でも「こんな感じで動画作ってください」って言ったら一瞬でそれっぽい動画ができてしまう時代になっています。
素早く安価に簡単に本物のようなコンテンツを生成展開できる中でどうやって信頼性の高い情報をリーチさせるのかっていうのを考えなくてはいけないと思っています。
能登半島地震に関するX投稿のデータを見たときに、コピペして投稿しているのは日本語話者以外と思われる方の投稿がほとんどだった。コンテクストを全く理解できていなくても大量の情報をリーチさせるような形で発信できるような時代になっています。
選挙ではそこまで見られていませんけども、選挙も含めて今後デジタル空間上の情報を見ていくうえで、このような認識が大切になるのかなという風に思っております
古田:私も、昨年が「AIによるディープフェイクの選挙元年」と言われていたことを踏まえて、世界各国の事例を調べて記事を書いたのですが、実際のところ、インドでも、欧州議会でも、アメリカでも、インドネシアでも、2024年の時点では、そこまでディープフェイクが大量に拡散されたという事例は見当たりませんでした。
ただし、2024年も後半になるにつれて事例は徐々に増えており、11月のアメリカ大統領選ではいくつか大きく話題になったものもありました。数は間違いなく増えています。
私自身は、AIはすでに「本物っぽいものを作る能力」は持っていると思います。ただし、まだ「人が拡散したくなるものを作る能力」は十分ではない。でも、もしAIがその能力を手に入れたとき、それが“ティッピングポイント”になって、ディープフェイクが爆発的に広がることになると危惧しています。
では、もうあっという間にまとめの時間となってしまいました。ここで登壇者の皆さまから、最後に一言ずつ、これまでの議論を踏まえてコメントをいただきたいと思います。
それでは今度は逆順で、西村さんからお願いします。
リサーチAPIの提供、変化する状況を把握して対応
西村:澁谷先生から学術研究のためのデータ提供という話がありましたが、TikTokではリサーチAPIという機能を備えていて提供をしています。ただ、日本市場ではまだ提供できておらず、ヨーロッパとアメリカ市場のみで提供していますので、それを拡大していくことが重要だと思っています。
私達自身がしっかりとやっていますと言っても、信頼性には限界があると思ってますので、第三者の方にしっかりと検証していただいて発表していただくことが重要だと思っています。
さて、この分野における私のまとめとしては、いま「情報インテグリティ」へのアプローチは非常に揺れ動いていると考えています。
たとえば他のプラットフォームでは、コミュニティノートの導入が進んでいたり、逆にファクトチェックを縮小する動きも見られたりと、各社の考え方や方針には違いが出てきています。
一方で、権威主義的な国家では、政治体制への批判を厳しく取り締まったり、積極的に投稿を審査したりという動きもあります。
いろいろな価値観の中で、しかも時間とともにこの価値観が変化する中で、我々プラットフォームがあるわけで、私たちも感覚を常に研ぎ澄ませ、状況を把握し、その時期、その場所、そのコンテンツにあった対応をしていく必要があると考えています。
私自身も、こうしたやり方でデジタルプラットフォームが健全に成長していけるよう貢献していきたいと思っています。
古田:リサーチAPIについて、ぜひ日本のファクトチェック団体にも提供をお願いできればと思います。
では、永田さん、お願いします。
横の連携でファクトチェックを 情報リテラシーの普及も積極的に
永田:健全な情報空間というのは、先ほどから出ている通り、関係する機関が総合的に作っていくものだと思います。
昨年の知事選を経験して感じたのは、短期的に対処しなければいけない課題もあるということです。たとえば、選挙はわずか17日間しかなく、その中で選挙結果の正当性が疑われるような事態が起きることは、あってはいけません。
兵庫の事例では、誹謗中傷に追い込まれて自死に至るようなケースもありました。こうした取り返しのつかない事態に即応するべきものは関係者全員の宿題として、中長期的なものとは別に考える必要があると感じています。
また、新聞社の立場で言えば、今後は「個別のファクトチェック」を行っていくことも増えると思います。ただし、個別にやると「神戸新聞は偏向している」と言われてしまうんですね。どこの報道機関であっても、一社だけでやると「気に入らない」と思っている人たちからそういう言われ方をする。
そこで現在、日本新聞協会の中では合議体で、あるいはそれぞれでファクトチェックに取り組んでいこうという議論が進んでいます。これは知事選後に始まった動きで、今後はこういった横の連携で新聞社がファクトチェック機能を強めていくことを私も期待しています。
また、情報リテラシーについても、新聞業界はこれまで関与が薄かったと思いますので、そこはより積極的になるべきだと感じています。
古田:信頼の問題というのは本当に重要で、私たちJFCも常にその課題に直面しています。
たとえば、一社でファクトチェックをしても「その社は偏っている」と言われる。一方で、新聞業界全体でやっても「新聞業界が偏っている」と言われることもある。この信頼の課題は、皆で考えなければいけない問題だと思います。
澁谷さん、お願いします。
誰もが偽情報問題に貢献できる 民主的な参加とインターネットを諦めない
澁谷:永田さんや古田さんからもお話があったように「総合的な対策」「多面的な取り組み」が必要だということに尽きると思っています。
技術的な対応策はもちろんですし、主体間の連携や協働、アルゴリズムの問題、プラットフォーム側の取り組み、ユーザーインターフェースの問題、そしてファクトチェックやリテラシー教育、どれをとっても重要です。
この問題の難しさは、どこかに責任の所在が明示化されているわけではないという点にあります。逆に言えば、誰もが偽情報問題に貢献できる、という捉え方もできると思います。
ユーザーも含めた一人ひとりが「これは自分たちの問題である」と改めて認識することが重要です。そこに対する民主的な参加を諦めない。デジタル空間の情報が怪しいと感じてあきらめてしまうような雰囲気が出てしまうことは良くないと思います。
民主的な参加を諦めない、インターネットを諦めない、そういった環境をどうやっていろいろな人が自分事として関わっていけるか。そういうネットワークを、私たちも含めて連携しながら作っていくことが大切だと考えています。
日本の2024年は世界にとっての2016年 今こそ総合的な対策を
古田:最後に私からも一言だけお話しさせていただきます。
私は2018年にBuzzFeed Japanの編集長としてファクトチェックに取り組んでいたのですが、その時に書いた記事で「日本の問題は『フェイクニュース』の強さよりもそれと戦う力の弱さだ」と指摘しました。
https://www.buzzfeed.com/jp/daisukefuruta/fake-hate-3
2024年の兵庫県知事選を見て、正直、当時と状況があまり変わっていないと感じました。2016年のアメリカ大統領選や、ブレグジットの時に世界はこの問題の重大性に気づき、対策を進めてきました。しかし日本では、対応のスタートが遅れました。私たちJFCの設立も2022年と、他の民主主義国に比べて遅れています。
ただし、我々も気づいたわけです。世界にとっての2016年が日本にとっての2016年です。今こそ本気で取り組まないといけない。澁谷さんの言葉にあった通り、「民主主義を諦めるわけにはいかない」。諦めてしまえば、民主主義そのものが成り立たなくなってしまいます。
そして、これも非常に印象的な言葉ですが「対策が遅れていたからこそ、誰しもが貢献できる」。この点はとても重要だと思っています。この点、パネル2でも、総合的な対策について引き続き議論していきたいと思います。
それでは、これにてパネル1を終了させていただきます。登壇者の皆さまに、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
(拍手)
アーカイブ動画とシンポジウム記事
情報インテグリティシンポ2025パネル討論1
情報インテグリティシンポ2025
基調講演1: 情報インテグリティ調査の概要
発表:合原兆二 氏(株式会社電通総研)
コメント: 山口真一 氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授)
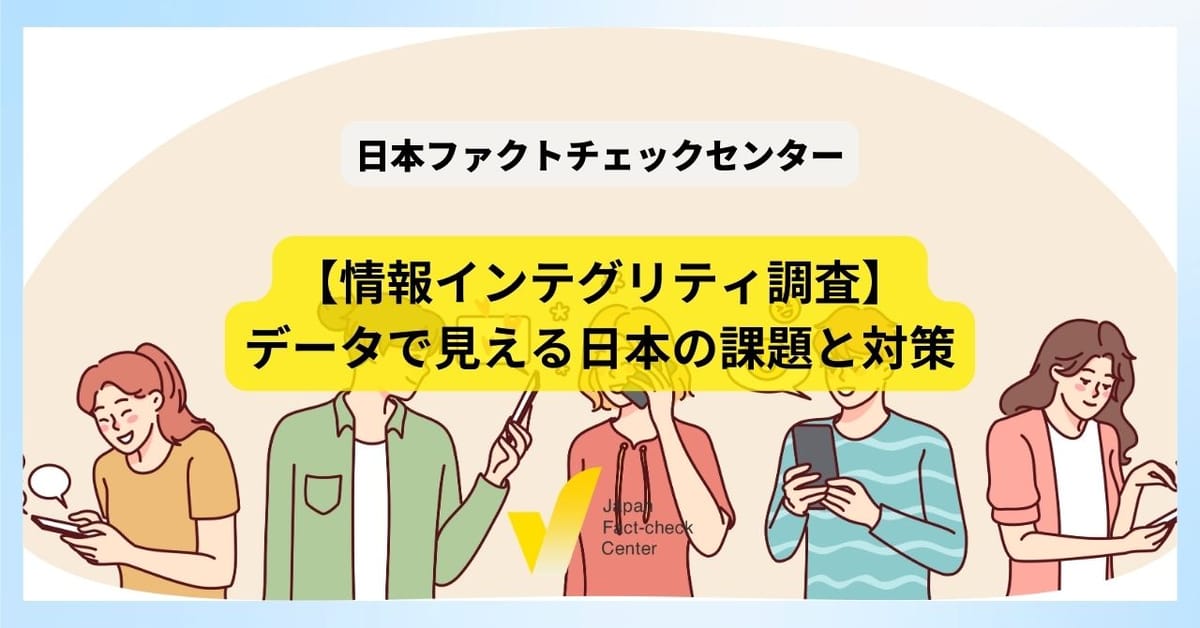
基調講演2: ファクトチェックとメディアリテラシーの現状と展望
発表:古田大輔(日本ファクトチェックセンター 編集長)
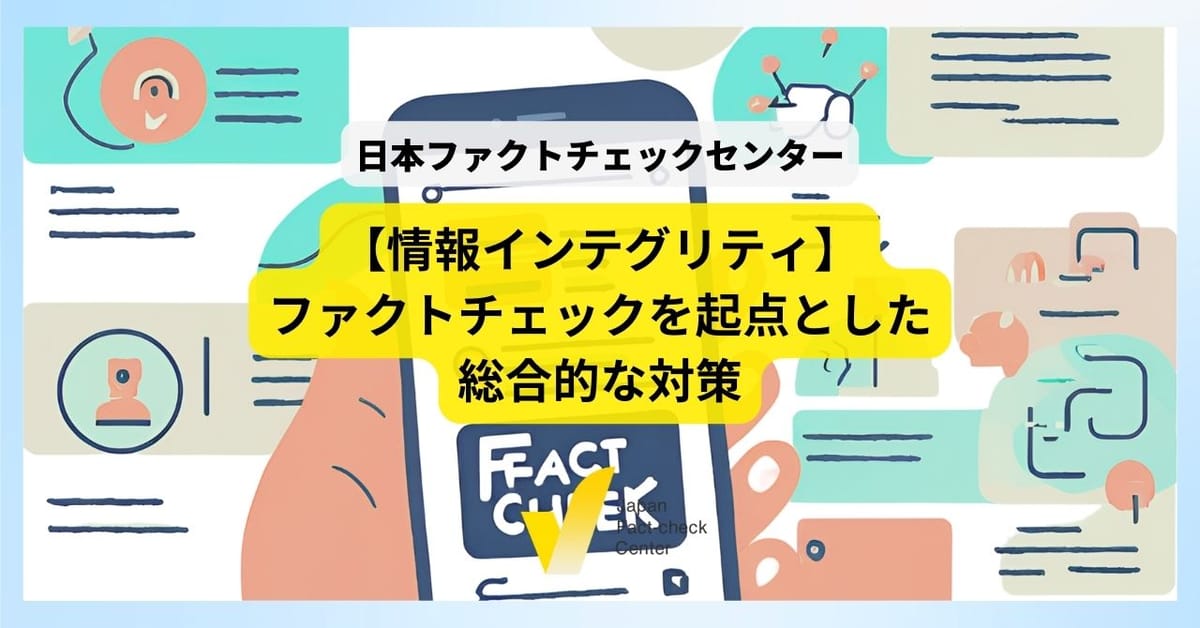
パネル討論2: 調和のある情報空間を目指す総合的な対策
モデレーター:古田大輔(日本ファクトチェックセンター編集長)
パネリスト
山本龍彦氏(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
桒原響子氏(公益財団法人日本国際問題研究所研究員)
吉田弘毅氏(総務省情報流通振興課企画官)

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。
毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。