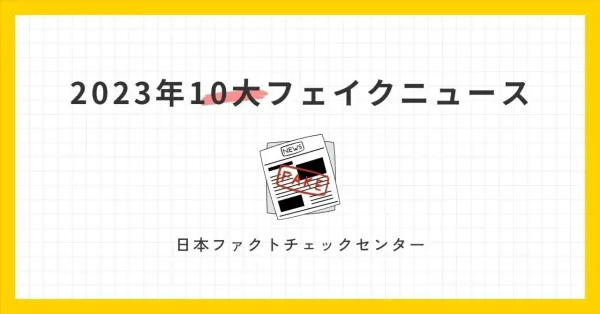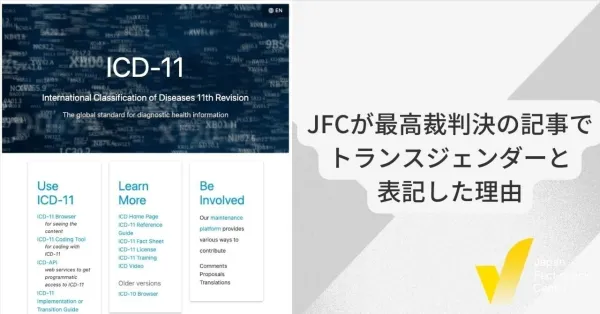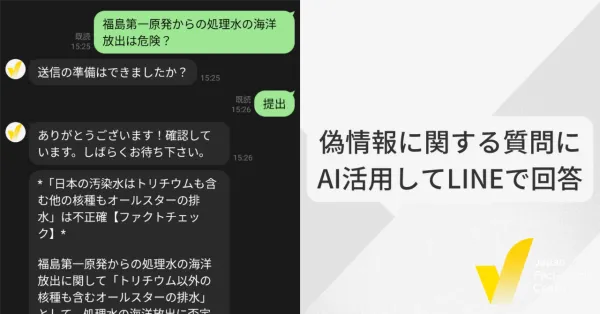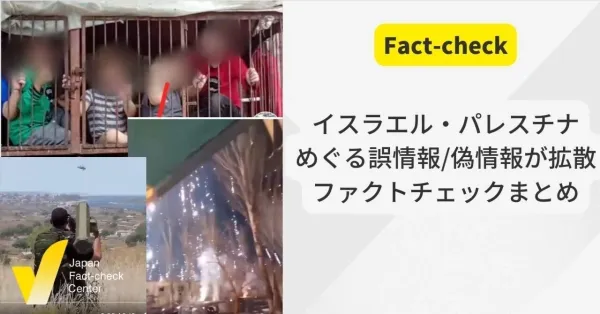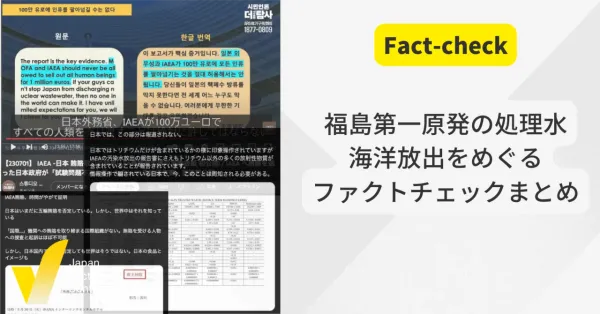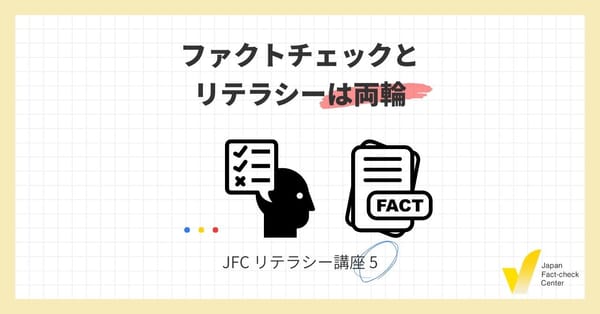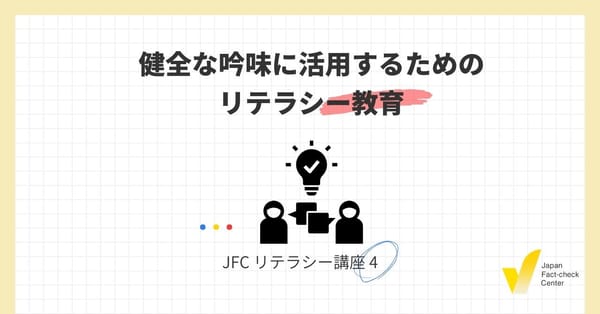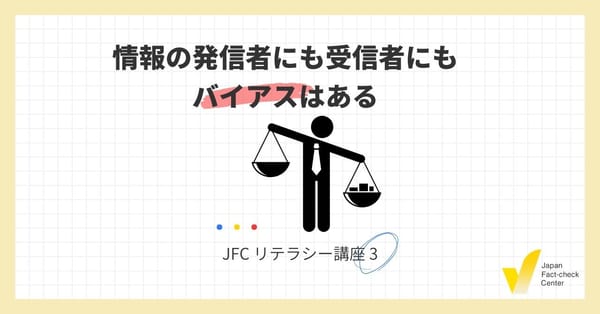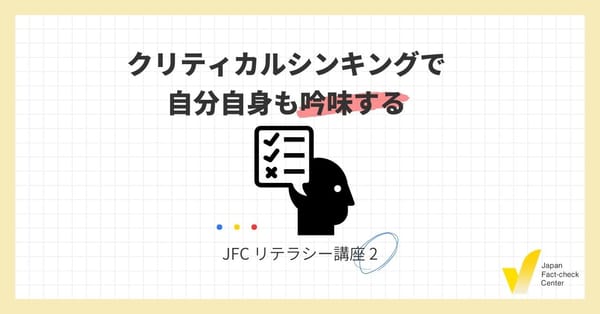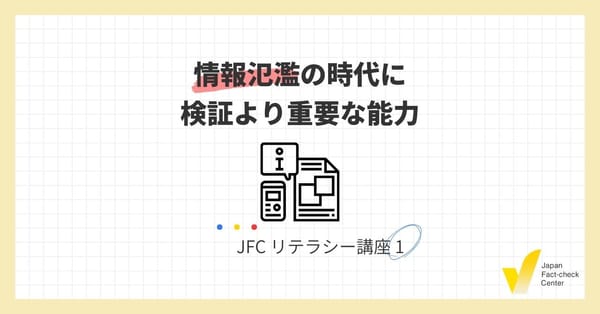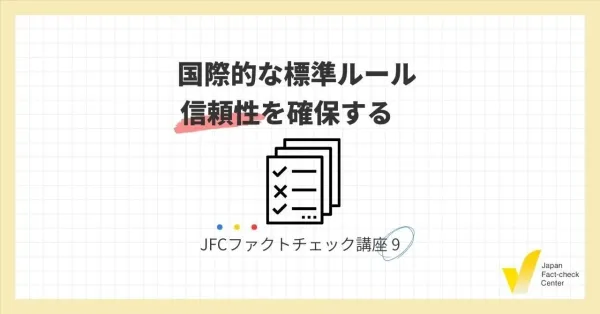その他
災害時に広がる偽情報5つの類型 地震や津波に関するデマはどう拡散するのか
地震や津波、洪水など大きな災害が発生すると、偽情報や根拠のない情報が拡散します。事実と異なる投稿や不確かな救助要請は、本当に助けを必要としている人たちへの支援を遅らせたり、妨げたりする恐れがあります。拡散しがちな偽情報・誤情報のパターンを知って、支援を妨げないようにしましょう。 災害時の偽情報の5類型 実際と異なる被害投稿 災害時に最も多く見られるのが、偽の被害報告だ。2024年1月1日の能登半島地震では、2011年の東日本大震災の津波の映像を使って、まるで能登半島地震の被害のように投稿する事例が相次いだ(例1、例2、例3、例4、例5 、例6)。 例2と例3を投稿した2つのアカウントは添付動画は異なるが、投稿文言は同じで「津波到達になった瞬間NHKのアナウンサーがすごい怒鳴ってる!危機感の伝わってくるアナウンスなので北陸新潟能登半島の方逃げてください」と書かれている。投稿内容をコピーしたと見られる。 例5の投稿は「石川県能登に大津波警報逃げろ」という文言に「#東日本大震災」というハッシュタグもついている。映像は東日本大震災のものだと示唆しているように読